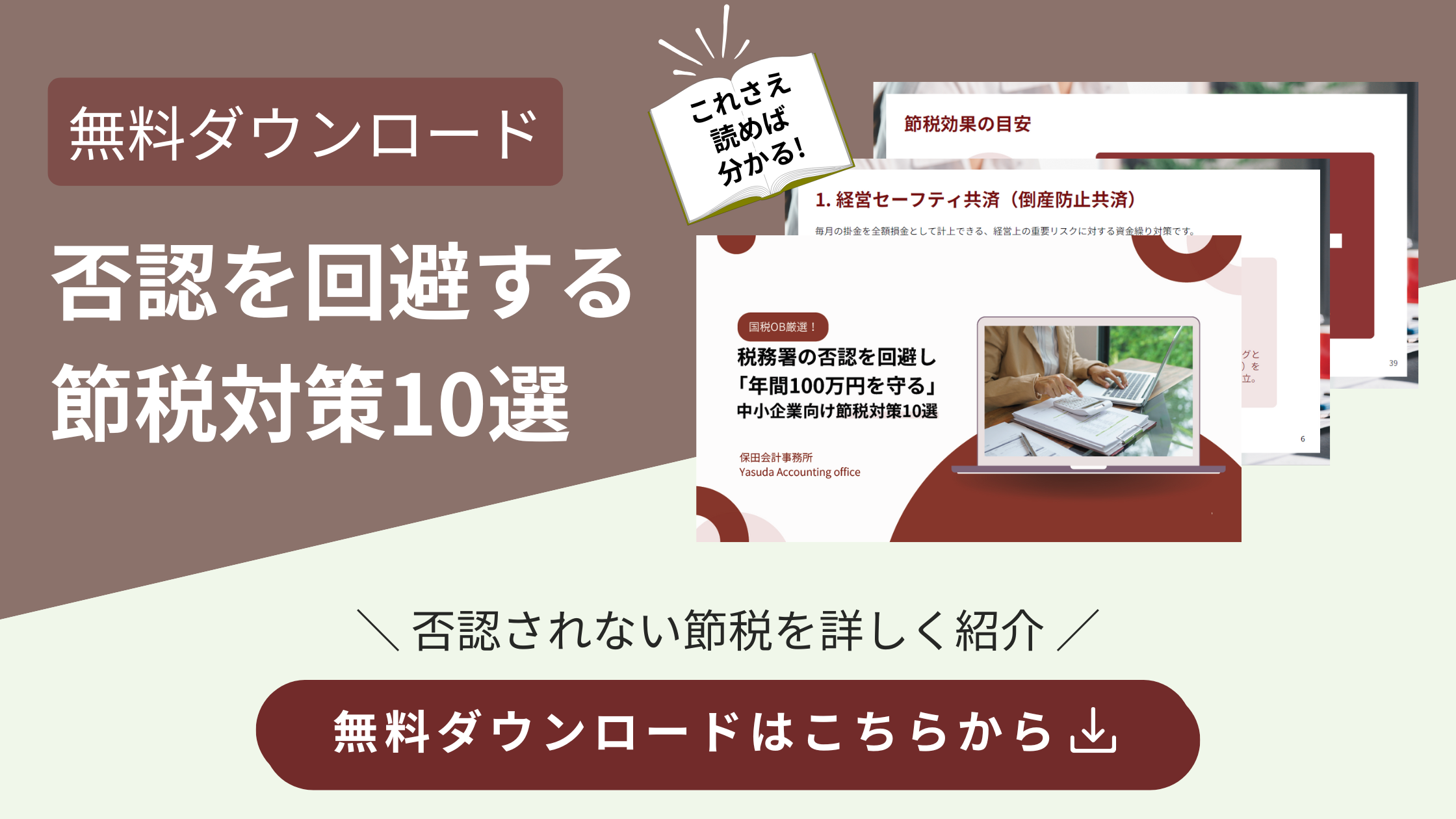税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
近年、副業やフリーランスの拡大に伴って、「夫婦で起業」「夫婦で会社設立」といった選択肢を検討するご夫婦が増えています。また、そのような方からは「夫婦で会社を設立したら節税になるって聞いたけど本当?」「夫婦起業は株式会社か合同会社かどちらがいいの?」といった質問を受けることが多いです。
そこで今回は、夫婦での会社設立に関して、「個人事業主との違い」「どんな会社形態を選ぶべきか(株式会社 or 合同会社)」「会社設立時にやるべきこと」等を詳しく解説します。
Table of Contents
1.夫婦で会社を作る人が増えている背景とは?
はじめに、「夫婦で会社を作る人が増えている背景」や「夫婦起業が注目される理由」などを確認します。
(1)共働き夫婦の新しい働き方としての「夫婦起業」
共働きが当たり前となった現代社会では、単に「二人で収入を得る」だけでなく、「夫婦でビジネスを運営する」という選択肢が現実味を帯びています。
背景には以下のような社会的な変化があります。
| ✓テレワークやフリーランスの普及
✓働き方改革による副業解禁 ✓個人での起業が容易になった環境(SNS・ネット広告の活用) ✓家族との時間を重視したライフスタイル志向 |
こうした流れの中で、「信頼できるパートナー=配偶者」と共にビジネスを立ち上げるというモデルが注目されています。
(2)副業からのステップアップとして会社を設立
特に多いのが、夫(または妻)が副業やフリーランスとして活動をしていて、そこに配偶者がサポート役として加わっているというケースです。このケースにおいて、事業が軌道に乗ってきた段階で、法人化を検討し始める夫婦が多いです。
例えば、メインの給与収入がある人で、副業の収入が年間300万円を超えてくると、個人事業主のままだと所得税率が上がりやすいことから、「夫婦で会社を作って、お互いに役員報酬を受け取る形にすれば、税負担を軽減できるのでは?」と考える方が増えていると思われます。
(3)夫婦起業はなぜ注目されているのか?
夫婦起業が注目される理由は、税制面の有利さだけでなく、以下の点でも優れていることが挙げられます。
| ✓生活と仕事の一体化を図り、ビジネスと家庭を柔軟に両立できる
✓家族のサポート体制が確立しやすい ✓お互いの得意分野を活かした事業運営が可能 ✓社会的にも「夫婦経営=安定感・信頼感がある」と評価されやすい |
具体的なメリット・デメリットについては、以下の記事をご参照になさってください。
【夫婦で会社設立②】夫婦で会社を設立するメリット・デメリットを徹底解説!
2.個人事業主との違いは?会社設立で変わる税務と社会保険の仕組み
すでに個人事業をしている人の場合、「今のまま個人事業主で続けるべきか、それとも法人化すべきなのか」多くの副業者・フリーランスが悩むポイントです。
ここでは、個人事業主と法人(夫婦設立)の違いを、「税務」と「社会保険」の観点から比較した上で、分かりやすく解説します。
(1)税率等の違い(所得税率 vs 法人税率)
個人事業主の場合は、所得金額が増えるほど税率も上がる累進課税が適用されます。一方で法人は、所得金額にかかわらず一定の法人税率が適用されるため、一定の利益を超えた場合に税率差異による節税効果が生まれます。
<税率等の比較表>
| 区分 | 個人事業主 | 法人(夫婦設立) |
| 税率体系 | 累進課税(最大45%)
+住民税10% |
法人税の実効税率(23%ほど※) |
| 所得の分散 | 不可 | 役員報酬で分散が可能 |
| 控除制度 | 青色申告特別控除など | 給与所得控除、経費拡大 |
| 決算時期 | 毎年12月31日 | 任意で設定可能 |
※ 所得400万円以下は21.3%ほど、所得800万円以下は23.1%ほど、所得800万円超は33.5%ほど
年間所得が500〜600万円を超えるあたりから、法人化による節税効果が実感できます。
また、夫婦で役員報酬や給与を分け合うことで、より効率的な節税が可能となります。
(2)個人事業と法人で異なる社会保険の加入義務
個人事業主は通常、国民健康保険・国民年金へ加入しています。一方で、法人化すると代表者等の役員は原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務化されます。
<社会保険に関する比較表>
| 項目 | 個人事業主 | 法人(役員) | 法人(従業員) |
| 健康保険 | 国民健康保険 | 社会保険(健康保険) | |
| 上記の保険料 | 所得割:12%ほど
均等割:7.6万円ほど (限度額106万円ほど) |
一般:9.91%
40歳~64歳:11.5% |
|
| 年金制度 | 国民年金(第1号) | 厚生年金(第2号) | |
| 上記の保険料 | 20万円ほど | 18.3% | |
| 加入義務 | 加入が必要
(任意継続等は除く) |
加入が必要
(非常勤は非加入が認められることもある) |
年収130万円(月収10.8万円)を超えると、扶養から外れ、加入が必要 |
| 保険料負担者 | 全額自己負担 | 会社と個人で折半 | |
| 給付内容 | 限定的 | 手厚い(傷病手当金など) | |
法人化によって、加入することとなる健康保険や厚生年金の方が傷病手当金や出産手当金などの保障制度が充実しており、将来的な年金受給額も大きくなるものの、社会保険の負担は基本的に法人の方が重たくなる点には注意が必要です。
そのため、夫婦で会社を設立する場合には、片方を従業員として、年収130万円の壁を意識した給与額を設定することで社会保険料の負担軽減になります。
(3)配偶者への給与支払いの可否と扱いの違い
個人事業主が配偶者に役務提供の対価を支払う場合、「専従者給与」という制度を利用することになります。一方、法人が配偶者に役務提供の対価を支払う場合には、役員報酬や給与として支払うことが可能です。
<専従者給与・役員報酬の比較表>
| 比較項目 | 専従者給与(個人事業主) | 役員報酬(法人) |
| 支払要件 | 生計を一にする15歳以上で常時従事していること | 法人の業務に従事していること |
| 金額の制限 | 届出金額以内という制限がある | 業務実態に応じて自由に設定可能 |
| 節税効果 | 所得分散による節税効果は限定的 | 所得分散による節税効果は高い |
このように、夫婦での会社設立では、「信頼できる身内に正当な対価としての報酬・給与を支払える」という点が大きな強みです。
3.夫婦での会社設立ではどんな会社形態を選ぶべき?株式会社と合同会社の違い
夫婦で会社を設立する際に、「株式会社」と「合同会社(LLC)」のどちらを選択すべきか迷うことが多いです。両者には明確な違いがあり、事業規模や目的に応じて適切な選択が重要です。
ここでは、それぞれの特徴を比較しつつ、夫婦経営における最適な形態を解説します。
(1)設立費用・手続きの簡単さは合同会社に軍配
合同会社は、2006年に施行された会社法によって創設された比較的新しい会社形態で、設立コストの低さと運営の自由度が特徴です。
<株式会社と合同会社の費用や特徴等>
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 設立費用(概算) | 約20〜25万円 | 約6〜10万円 |
| 公証人の定款認証 | 必要 | 不要 |
| 設立にかかる期間 | 約2週間 | 約1週間 |
| 経営の柔軟性 | 株主・取締役制度で制限あり | 出資者=経営者で自由度高い |
| 決算公告の義務 | あり | なし |
上記の表からも分かるように、スモールスタートや設立費用を抑えたい夫婦には、合同会社が適合します。
(2)対外的な信用力や将来の資金調達を考えるなら株式会社
株式会社は対外的な信用力が高く、資金調達手段が豊富である点がメリットです。
将来的に取引先を増やす、従業員を雇用する、投資を受け入れるといった成長を見据えるなら、株式会社が選ばれる傾向にあります。
そのため、株式発行による資金調達をしたい場合、上場(IPO)も視野に入れる場合には、株式会社が適合します。
(3)自社株の相続対策を考えるなら株式会社
設立した法人の内部留保が大きくなると自社株の株価は上昇していきます。そのため、法人で毎年それなりの利益を計上する予定がある場合には、自社株の株価上昇に備え将来の相続対策も見据えておく必要があります(将来の財産が5千万円越を想定していない場合には相続対策の重要性は低いです)。
合同会社では出資者=経営者ですが、株式会社では所有と経営の分離が図られており、株主と経営者は別々に機関設計することができます。
そのため、株式会社であれば、以下のように株主と経営者を分けることで相続対策が可能となります。
| 会社形態 | 株主 | 経営者
(役員) |
相続への影響 |
| 株式会社 | 子供 | 夫婦 | 子供を株主とすることで、設立した会社の自社株としての価値が上昇した場合であっても夫婦の財産に含まれないため、相続対策になります。 |
| 株式会社 | 妻 | 夫 | 妻を株主とすることで、設立した会社の自社株としての価値が上昇した場合であっても夫の財産に含まれないため、相続対策になります。
(ただし、配偶者には1億6000万円の控除があるため、夫の相続財産が2億円ほどなければ相続対策を見据える必要はあまりありません) |
上記のような工夫ができるため、相続対策には、株式会社が適合します。
ただし、合同会社であっても、定款に定めれば業務を執行しない社員の立場を作ることができます。
そこで、例えば、業務を執行しない社員を子ども、業務を執行する社員を夫婦として、子どもの出資額を多くすることで、株式会社に近い形での相続対策も可能です。
(4)夫婦経営におすすめの会社形態とは?
多くの夫婦起業にとっては、まずは合同会社でスタートすることが現実的です。
主な理由としては、以下の事項が挙げられます。
| ✓コストが安い
✓意思決定の自由度が高い ✓株主・取締役の区分がないため、役割分担が柔軟 |
将来的に事業が拡大してきた段階で、「合同会社から株式会社へ組織変更」することも法的手続きをとれば可能であるため、上記(2)(3)に一致しない場合には、いったん合同会社でスタートすることがおすすめです。
(5)こんな夫婦にはこの会社形態
夫婦起業の会社形態に迷った場合には、以下の表をご参考になさってください。
| 夫婦のタイプ | おすすめの会社形態 |
| 節税+シンプルな夫婦経営を目指す | 合同会社 |
| しばらく夫婦だけで完結したい | 合同会社 |
| スタートアップ企業として成長・融資を狙う | 株式会社 |
| いずれ第三者(社員・投資家)を迎える予定 | 株式会社 |
| 自社株の株価上昇に備え相続対策をしておきたい | 株式会社 |
会社形態の選択は、今後の事業戦略を左右する重要なポイントです。そのため、夫婦間のビジョンをすり合わせたうえで、専門家の助言を受けながら最適な形態を選択することが大切です。
4.会社設立時にやるべきこと(夫婦でスムーズにスタートするための5ステップ)
会社を設立を思い立ったら、すぐに事業開始ができるわけではありません。設立時に行うべき事務手続きや制度設計をきちんと理解しておくことが、トラブルなくスムーズに経営をスタートするコツです。
ここでは、設立後に必要なステップを5つに分けてわかりやすく解説します。
これら5ステップを着実に実行することで、会社設立後の混乱を防ぎ、安心して夫婦経営をスタートできる体制が整います。
(1)定款の作成と役割分担の明確化
会社設立時には「定款(ていかん)」という会社のルールを定めた書類を作成します。定款には、目的・商号・本店所在地・事業内容・発起人などを記載しますが、夫婦で経営する場合には「役割分担」の設計も重要です。
<ここで決めておくべきポイント>
| ✓代表取締役をどちらが担うか
✓取締役や業務執行権限の範囲 ✓お互いの報酬額と支払い時期 ✓業務内容の分担(営業、経理、広報など) |
この段階で、曖昧さを排除しておくことで、後々の意見の食い違いを防ぐことができます。
(2)法人登記と必要書類の準備
定款を作成・認証した後は、法務局で法人登記の手続きを行います。法務局で書類審査が終わり、登記完了をもって「法人として正式に成立」します。なお、法人設立日は登記完了日ではなく、登記申請書類を法務局に提出した日(受理された日)となります。
<登記に必要な書類の一例>
| ✓設立登記申請書
✓定款 ✓発起人の決定書 ✓発起人の印鑑証明書 ✓取締役就任承諾書 ✓資本金の払込証明書 |
登記が完了したら、法人の印鑑証明書、履歴事項全部証明書なども取得し、銀行口座開設や各種届出に使用します。
(3)税務署・年金事務所への各種届出
会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・年金事務所などにさまざまな届出が必要です。提出期限があるため、注意しましょう。
<主な届出>
| ✓法人設立届出書:
【会社設立後の提出書類①】税務署への法人設立届の概要と書き方(記入例あり)
【会社設立後の提出書類②】地方自治体への法人設立届の概要と書き方(記入例あり)
✓青色申告の承認申請書: 【会社設立後の提出書類③】青色申告承認申請の概要と書き方(記入例あり)
✓給与支払事務所等の開設届出書:
✓源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:
✓健康保険・厚生年金の新規適用届(年金事務所): |
これらを漏れなく行うことで、正当な税務処理と社会保険の適用が可能になります。
(4)給与・社会保険の設定と支払いスケジュール
法人化すると、夫婦それぞれに役員報酬または給与を支払う体制を整える必要があります。役員報酬は、「定期同額給与」として毎月同じ金額を支払うことが原則です。
また、社会保険の加入手続き後は、保険料を会社と役員の折半で支払っていくことになります。
<給与・社会保険に関して準備しておくべきこと>
| ✓役員報酬の額と支給日を定款または株主総会議事録で決定
✓源泉徴収・住民税・保険料の納付スケジュールの確認 ✓会計ソフトや税理士と連携し、給与計算体制を整備 |
(5)専門家(税理士・社労士)との連携体制を整える
会社経営を夫婦だけで全てこなすのは現実的ではありません。特に税務・会計・社会保険の分野は複雑かつ重要なため、信頼できる専門家との連携は必須です。
<おすすめの専門家>
| ✓税理士:節税アドバイス、決算書作成、法人税申告
✓社労士:社会保険・労働保険の手続き、就業規則作成 ✓司法書士:法人登記サポート |
専門家に依頼することで、制度トラブルや申告ミスのリスクを最小化し、安心して経営に集中できます。
5.夫婦起業のよくあるQ&A
夫婦で会社を設立するにあたり、実際に多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式で解説します。制度や実務に関わるポイントは、誤解しやすい部分でもあるため、正確な理解が大切です。
Q1:夫婦で会社を設立するメリット・デメリット
A1:主なメリット・デメリットは下表の通りです。
<主なメリット>
| ✓所得分散による節税効果
✓社会保険料の最適化 ✓意思決定の速さ ✓信頼関係を活かした役割分担ができる ✓経費の活用がしやすくなる ✓将来的な相続や事業承継がスムーズになる |
<主なデメリット>
| ✓プライベートとビジネスの境界が曖昧になりやすい
✓トラブル時に夫婦関係に悪影響を及ぼす可能性 ✓雇用契約・給与支払いに関する法的な注意点 ✓社会保険料の負担が増えることがある |
具体的なメリット・デメリットについては、以下の記事をご参照になさってください。
【夫婦で会社設立②】夫婦で会社を設立するメリット・デメリットを徹底解説!
Q2:夫婦での会社設立を検討すべきなのはどんな人?
A2:副業を含めた所得が700万以上ある人、配偶者がすでに事業に関わっている人、節税・社会保険コストを見直したい人、将来的にフルタイムの夫婦経営を視野に入れている人
なお、夫婦での会社設立を検討すべき人については、以下の記事の「4.夫婦で会社設立を検討すべき人の特徴とは?」に詳細がありますので、是非ご参考になさってください。
【夫婦で会社設立②】夫婦で会社を設立するメリット・デメリットを徹底解説!
Q3:配偶者に給与を払ってもいいの?
A3:はい、法人化すれば配偶者に役員報酬や従業員給与として支払うことが可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です
| ✓役員報酬として支払う場合は、「定期同額給与」(毎月同額)である必要があります。
✓業務内容に見合った金額でなければ、税務署に経費として認められない可能性があります。 ✓配偶者が従業員として勤務する場合には、労働契約書や就業規則の整備が求められます。 ✓税務署とのトラブルを避けるには、税理士に報酬設計の相談を行う方が安心です。 |
Q4:配偶者は役員と従業員のどちらがいいの?
A4:配偶者も積極的に経営参加したい場合や老後の年金受給額を増やしたい場合には「役員」を選択し、役員報酬をしっかり受けることをおすすめします。
一方で、働く時間が限られる場合や、扶養の範囲内で働きたい場合には「従業員」を選択することをおすすめします。
配偶者は役員と従業員のどちらが有利かについては、以下のLink先の記事もご参考になさってください。
【夫婦で会社設立③】配偶者(妻)は役員と従業員のどちらがいいか詳しく解説!
Q5:扶養から外れるのはどんなとき?
A5:配偶者が年間130万円以上の収入を得ると、健康保険や税制上の扶養から外れる可能性があります。
<扶養の取扱い>
| 区分 | 扶養のまま | 扶養から外れる |
| 年間収入の目安 | 130万円以下 | 130万円超 |
| 社会保険(健康保険) | 被扶養者として継続 | 本人が社会保険に加入 |
| 所得税の配偶者控除 | 123万円以下なら受けられる | 制限される |
※ 役員報酬の場合には、社会保険加入義務が生じるため、130万円以下であっても扶養から外れます。
Q6:自宅を事務所にすると何が経費になる?
A6:自宅兼事務所にすることで、例えば、以下のような費用を事業経費として計上することが可能です。
<費用の例示>
| ✓家賃
✓電気・水道・ガス代 ✓インターネット通信費、電話料金 ✓事務スペースの備品・家具費用 |
<注意点>
| ✓経費にできるのは「業務で使用している部分」に限られます(按分が必要)
✓按分率(事務スペースの割合など)は合理的な根拠が必要 ✓法人契約に変更した方が費用として認めてもらいやすくなる傾向あり |
税務調査でもチェックされやすいポイントのため、税理士に相談しながら判断しましょう。
Q7:離婚時の会社の扱いはどうなる?
A7:離婚によって会社の経営権や出資比率に関するトラブルが生じるリスクがあります。
例えば、夫婦で50%ずつ出資している場合には、離婚後も共同経営を続けなければならず、意思決定に支障が出るケースもあります。
<回避策>
| ✓出資比率に差をつけておく(例:夫70%、妻30%)
✓定款に株式譲渡制限や代表権のルールを設けておく ✓万が一のための「事業承継・経営交代プラン」を整備 |
感情的な対立がビジネスに悪影響を与えないよう、法人設計の段階から法的・経営的リスク管理が必要です。
6.まとめ
以上今回は、夫婦での会社設立に関して、「個人事業主との違い」「どんな会社形態を選ぶべきか(株式会社 or 合同会社)」「夫婦で会社設立を検討すべき人の特徴」等を詳しく解説させていただきました。
夫婦で会社を設立することは、信頼関係に基づく経営体制を築ける点や、節税・社会保険面でのメリットを得られる点などから、近年ますます注目を集めています。
個人事業主と比較すると、法人化することで正式に配偶者に役員報酬や給与を支払えることができ、所得を分散しやすくなり、税負担の軽減や経費の活用幅が広がるといった制度的なメリットが期待できます。
ただし、会社形態の選択(合同会社か株式会社か)や社会保険の負担、将来の相続や事業承継といった観点も加味する必要があり、安易に始めるのではなく、夫婦間での話し合いと将来のビジョンの共有が欠かせません。
設立後には税務・労務の届出や報酬設計といった実務も待っており、専門家との連携を前提とした体制づくりが経営の安定に繋がります。
副業が軌道に乗ってきた人や、すでに夫婦で事業を運営している人は、法人化の検討によってより持続可能なビジネスモデルを築ける可能性があります。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、「夫婦での会社設立」をこれまで多数コンサルティングしておりますので、ご興味等ございましたら、お気軽にご連絡ください。