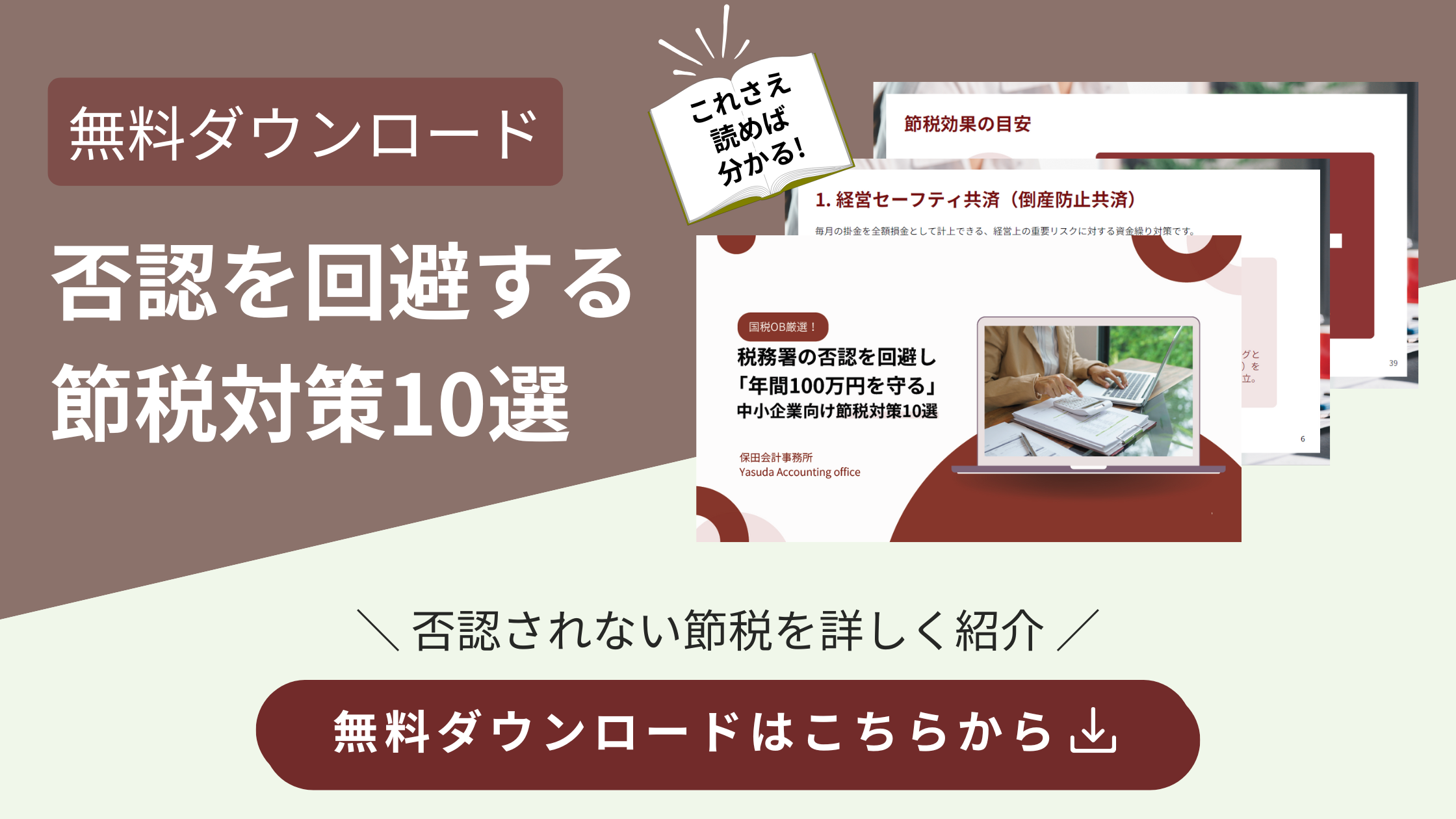税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
近年、「夫婦で会社を設立する」「夫婦で一緒にビジネスを始める」といった“夫婦起業”が注目を集めています。
そこで、今回の記事では、そんな「夫婦での会社設立」について、「基本的な手続き」から「役員や従業員としてのメリット・デメリット」、「注意点」に至るまで、わかりやすく解説します。
夫婦での起業を検討している方にとって、現実的な一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。
Table of Contents
1.なぜ今「夫婦で起業」が注目されているのか
共働き世帯が増える中で、夫婦の力を合わせて起業する「夫婦起業」が注目されています。背景には以下のような社会的要因があります。
| ✓柔軟な働き方を実現したいというニーズの増加
✓育児と仕事を両立するための選択肢としての独立 ✓夫婦での資産形成や事業承継を視野に入れた計画的な起業 |
特に「いずれは独立したい」と考え、副業をしている人にとっては、最も身近なビジネスパートナーである妻との起業は、現実的な選択肢になっています。
なお、個人事業主との違いやどんな会社形態を選ぶべきかについては、以下の記事もご参考になさってください。
【夫婦で会社設立①】個人事業主との違いや選ぶべき会社形態等を網羅的に解説!
2.夫婦で会社設立する際の基本知識
夫婦で会社を設立する場合、通常の会社設立と大きな違いはありませんが、以下のような手続きが必要です。
(1)会社設立の主な流れ(株式会社の場合)
①会社の基本事項(商号・目的・資本金など)の決定
②定款の作成・認証
③資本金の払込
④登記申請(法務局へ)
⑤税務署や社会保険事務所への届け出
夫婦で共同出資する場合は、出資比率やそれに伴う役割分担、報酬の設定が重要になります。
(2)出資比率・役割分担の考え方
出資比率は会社の経営権に直結するため、以下のような視点で決定します。
| ✓夫婦で平等に経営したい → 50:50
✓実質的な経営権は夫が持つ → 70:30 や 80:20 など ✓相続・贈与税対策を考慮する場合 → 10:90 |
役割分担については、実務に関与するかどうか、責任をどこまで持つか、という視点で決定します。
また、相続・贈与税対策では子供への配分も検討が必要です。
(3)配偶者に役員報酬や給与を支払うことで所得分散ができる
法人を設立すると、夫婦それぞれに役員報酬や給与を支払うことが可能になります。これにより、所得を分散させて所得税と住民税の負担を軽減することができます。
3.配偶者を役員にする場合のメリット・デメリット
ここでは、配偶者を役員にする場合の「メリット・デメリット」と「社会保険の加入義務」について解説します。
なお、夫婦で会社を設立するメリット・デメリットについては、以下の記事もご参照になさってください。
【夫婦で会社設立②】夫婦で会社を設立するメリット・デメリットを徹底解説!
(1)配偶者を役員にする場合のメリット
配偶者を役員にすると、以下のようなメリットが期待できます。
| ✓所得分散により所得税・住民税が節税できる(従業員でも同様)
✓役員報酬や社会保険料が損金算入できるため、法人税が圧縮できる ✓役員報酬は高額な報酬設定もできる(ただし、経営への関与がなければ否認される) ✓社会保険に加入でき、将来の年金や傷病手当金などの恩恵を受けやすくなる(社会保険料の負担が生じることはデメリット) ✓責任感を持ち働いてもらえる ✓役員としての肩書があると仕事(営業活動や取引先との交渉など)がやりやすくなる可能性がある |
(2)配偶者を役員にする場合のデメリット
一方で、配偶者を役員にすると、以下のようなデメリットもあります。
| ✓社会保険の加入義務が生じる(詳細は(3)を参照)
✓役員の場合には定期同額給与で支払うことになるため、途中で役員報酬を下げたり上げたりすると税務上否認されてしまうことがある ✓法的責任を負う(会社法上の善管注意義務、損害賠償責任など) ✓会社の倒産時に連帯保証人であれば債務負担のリスクがある |
また、他の従業員がいる場合には、社内での公平感が損なわれ、モチベーション低下につながるリスクがあります。
(3)常勤役員は社会保険への加入が必要
配偶者を役員にした場合、常勤役員であれば社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務づけられます。
これにより、配偶者が社会保険上の扶養に入っていた場合には、扶養から外れることになり、社会保険料の負担が増加します。
社会保険料は個人と法人で折半しますが、個人と法人をあわせ、標準月額報酬(4月~6月の平均役員報酬額を等級にあてはめたもの)の30%ほどの負担が発生するため、事前に社会保険料のシミュレーションを行うことをおすすめします。
なお、非常勤役員については、社会保険への加入は不要ですが、扶養の範囲(年収130万円)を超える場合には、国民健康保険などへの加入が必要となります。
また、合同会社の役員を非常勤役員とする場合には、「業務執行権のない社員」として定款で定めることが必要(登記は不要)です。
4.配偶者を従業員にする場合のメリット・デメリット
ここでは、配偶者を従業員にする場合の「メリット・デメリット」と「社会保険と労働保険の加入要件」について解説します。
(1)配偶者を従業員にする場合のメリット
配偶者を従業員にすると、以下のようなメリットが期待できます。
| ✓所得分散により所得税・住民税が節税できる(役員でも同様)
✓加入要件を満たさない場合には社会保険・雇用保険への加入が不要(詳細は(3)参照) ✓年の途中で給与額を変更したり、賞与を支給したりすることができる ✓他の従業員もいる場合、納得してもらいやすい |
(2)配偶者を従業員にする場合のデメリット
一方で、配偶者を従業員にすると、以下のようなデメリットもあります。
| ✓労働保険(雇用保険・労災保険)の加入義務が生じる(詳細は(3)参照)
✓退職金に関して、税務署が認めてくれる金額が役員に比べて低くなる可能性がある |
(3)社会保険と労働保険(雇用保険・労災保険)の加入要件
社会保険と労働保険(雇用保険・労災保険)のそれぞれの加入要件は以下の通りです。
①社会保険の加入要件
社会保険の加入要件は、次の通りです。
| ✓常時雇用されている従業員(正社員など)
✓週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者(※) |
※ ただし、所定労働時間と所定労働日数が、4分の3未満の場合であっても、次の3つの要件すべてを満たす人は被保険者となります。
| ✓勤務先の被保険者の総数が常時51人以上
✓週の所定労働時間が20時間以上あること ✓賃金の月額が8.8万円以上であること(106万円の壁) ✓学生でないこと |
被保険者の総数が常時50人以下の会社で、従業員となる配偶者を社会保険に加入させたくない場合には、パート(従業員の4分の3未満の労働時間)にすれば、給与月額が8.8万円以上(106万円の壁)であっても社会保険に加入する必要はありません。
ただし、年収130万円を超える場合には、扶養から外れるため、国民健康保険などへの加入が必要となることから、注意が必要です。
②労働保険(雇用保険・労災保険)の加入要件
雇用保険の加入要件は、次の通りです。
| ✓31日間以上働く見込みがあること
✓所定労働時間が週20時間以上であること ✓学生ではないこと(例外あり) |
これら3つの加入条件を満たした場合、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に限らず、すべての労働者が雇用保険の加入対象者となります。
一方で、労災保険については、基本的に全ての労働者が加入する必要があります。
そのため、配偶者を従業員とする場合において、雇用保険に加入させたくない場合には、所定労働時間を週20時間未満にする必要があります。
5.配偶者を役員と従業員のどちらにするかのポイント
ここでは、配偶者を「役員」と「従業員」のどちらにするか、決めるためのポイントを解説します。
(1)家族構成・将来設計・社会保険に応じた選択
例えば、次のような条件があると、役員と従業員のどちらにするか選択しやすいです。
| ✓配偶者も積極的に経営参加:
「役員」を選択し、役員報酬をしっかり受ける ✓働く時間が限られる: 「従業員」を選択し、扶養の範囲内で働く ✓老後の年金受給額を増やしたい: 「役員」を選択し、社会保険に加入 |
(2)事業承継・相続を見据えた選択
将来的に配偶者に事業を承継させたいと考えている場合には、はじめから「役員」を選択しておいたほうが後の役員変更も不要でおすすめです。
また、はじめから出資者(株式会社の株主、合同会社の社員)にしておくことで自社株の移転に関する税金(相続税や贈与税、譲渡税など)を節税することも可能となります。
なお、子供に事業を承継させたいと考えている場合には、会社の出資構造・役員構成は長期的視点で考えることが重要です。
6.配偶者を役員もしくは従業員にする場合の注意点
ここでは、配偶者を役員もしくは従業員にする場合の注意点を3つ確認します。
(1)支給額をいくらにするかシミュレーションが必要
支給額の設定次第で、所得分散の効果や社会保険料の負担増加、会社の法人税などが異なります。
また、個人側の手取額と法人側の手取額がいくらになるかについては、会社設立にあたって重要な要素となりますので、支給額ごとの手取額シミュレーションをできるかぎり行うことをおすすめします。
例えば、役員報酬・給与を計上する前の所得を1千万円、役員報酬・給与の支払総額を600万円とした場合、本人の役員報酬を500万円、配偶者を従業員として給与100万円とすることで、個人と会社の合算手取額が大きくなります。
夫婦や役員報酬・給与を支給する場合の手取額のシミュレーションについては、次の記事もご参考になさってください。
【夫婦で会社設立④】夫婦の役員報酬・給与のシミュレーション結果を解説!
(2)実態がない役員報酬や給与は認められない
配偶者に支給する役員報酬や給与を経費として計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。
| ✓実態のある労働があること(経営者の場合でも最低限、株主総会等への出席が必要)
✓労働の内容に見合った報酬額であること ✓給与支払いが定期的であること(役員の場合には定期同額給与でないと費用処理できない) |
また、親族への役員報酬や給与は税務調査の際に議論となりやすい項目であるため、次のような対策によって、調査官に勤務実態を示すことができるようにしておくことが大切です。
<役員報酬や給与を否認されないための対策>
| ✓従業員の場合には雇用契約書、役員の場合には株主総会や取締役会等の議事録を整備すること
✓出勤簿や勤務日誌、業務日報をきちんと残すこと ✓業務分担を明確にして、実際に労務提供している証拠(写真など)を残すこと ✓名刺を作成すること ✓組織図にのせ、社内に机などを用意すること ✓役員の場合には、税務調査の初日に顔を出すこと |
(3)夫婦間の金銭トラブル防止のための契約書
夫婦間のトラブル防止のため、業務内容を明確にしておくことをおすすめします。
できれば、次のような契約書の作成が望ましいです。
| 従業員の場合:雇用契約書
役員の場合:委任契約書、職務分掌書 |
契約書等がない場合には、いざという時に口論や責任の押し付け合いになる可能性があります。
7.まとめ
以上、今回の記事では、「夫婦での会社設立」について、「基本的な手続き」から「役員や従業員としてのメリット・デメリット」、「注意点」に至るまで、わかりやすく解説いたしました。
夫婦で会社を設立する際、配偶者を「役員」にするか「従業員」にするかは、経営への関わり方や働き方、将来の事業承継や税務・社会保険への影響などを踏まえて慎重に検討する必要があります。
どちらの形を選んでも所得の分散による節税効果が期待できますが、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
例えば、配偶者が経営に深く関わる場合や将来の事業承継を見据えるのであれば、「役員」としての参画が適しています。一方で、働く時間が限られていたり、社会保険の扶養内で活動したい場合には「従業員」としての雇用が現実的です。
また、役員報酬や給与の支給にあたっては、税務上のリスク回避のためにも勤務実態をきちんと示せるよう準備しておくことが重要です。
夫婦で起業することは、人生や家庭のあり方に大きな影響を与える選択肢です。だからこそ、将来を見据えて制度や税制を理解しながら、自分たちに合った形を見つけていくことが大切です。
は役員と従業員の-どちらがいいか詳しく解説!.png)