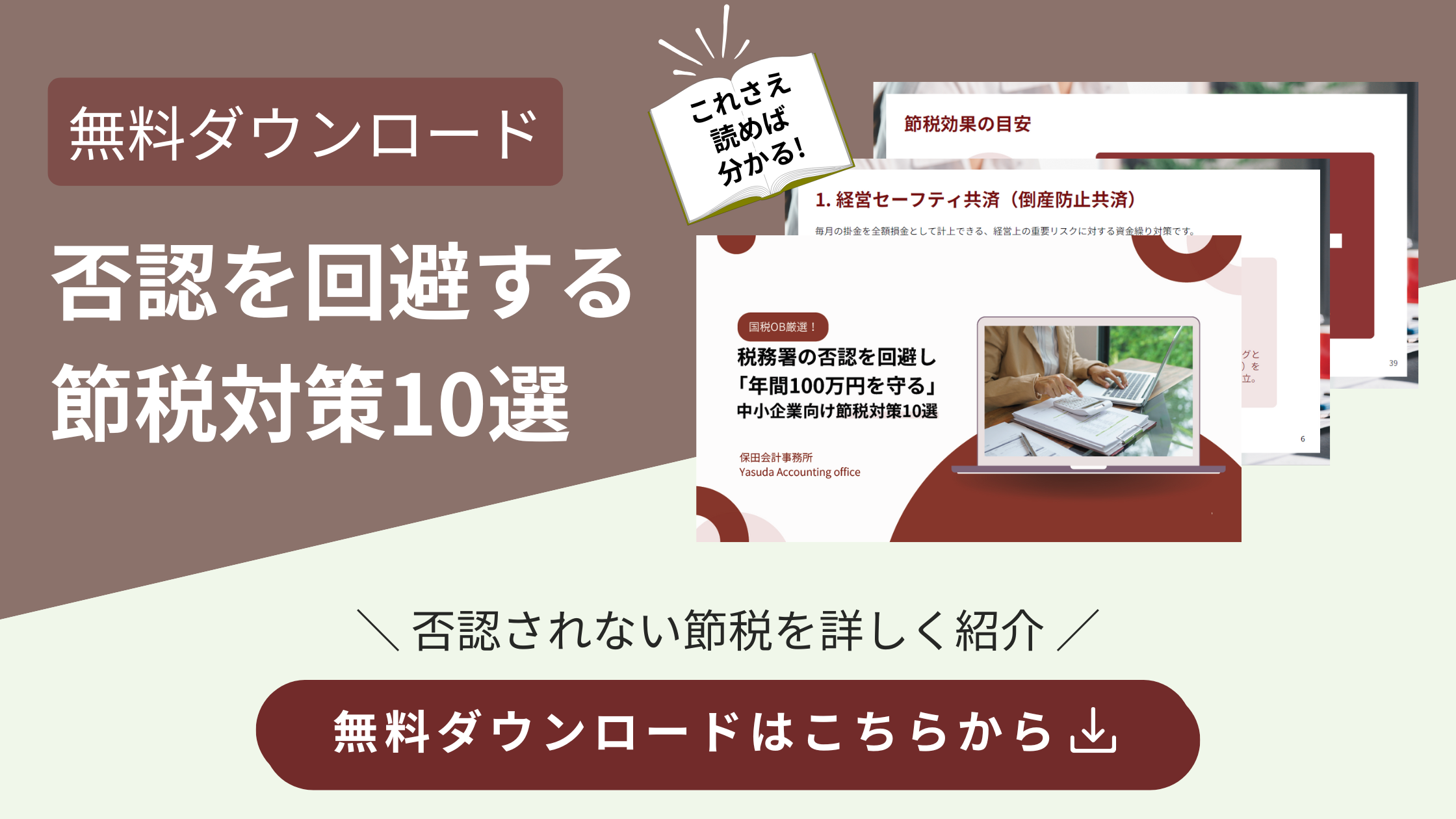税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
中小企業の経営者にとって、「節税」と「資金繰りの安定」は常に大きな課題です。金融機関からの融資は、審査や担保・保証の制約があり、必要なときに思うように資金を確保できないケースも少なくありません。
その中で、国が運営する「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」は、節税効果と資金繰り対策を同時に実現できる制度として注目されています。
本記事では、「経営セーフティ共済」の制度の仕組みやメリット・デメリット、返戻率(解約手当金)、税金、出口戦略までを、実際のシミュレーションを交えながら詳しく解説します。
中小企業オーナーが「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」を節税対策として活用するためのガイドとしてお使いください。
Table of Contents
1.経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは何か
まずは制度の基本を正しく理解することが重要です。
(1) 制度の概要
経営セーフティ共済は、正式名称を倒産防止共済と言い、中小企業倒産防止共済法に基づき中小企業基盤整備機構(中小機構) が運営する共済制度です。
本来の目的は「取引先が倒産した場合に中小企業の連鎖倒産を防ぐ」ことで、掛金を積み立てることで、取引先倒産時に掛金の10倍まで借入ができる仕組みになっています。
(2) 加入資格(対象となる中小企業者の範囲)
業種ごとに加入できる中小企業の範囲が決まっています。
| ✓製造業・建設業:従業員300人以下
✓卸売業:従業員100人以下 ✓小売業:従業員50人以下 ✓サービス業:従業員100人以下 |
幅広い業種の中小企業が利用可能で、個人事業主も加入できます。
また、引き続き1年以上事業を継続している必要があるため、設立1期目の法人は原則として、経営セーフティ共済に加入することはできません。
(詳細は後述のQ&Aを参照)
(3) 掛金の仕組み(掛金の範囲・積立上限)
掛金月額の範囲や積立の上限は次の通りです。
| ✓掛金月額:5,000円~20万円(5,000円単位で自由に設定)
✓積立上限:800万円まで積立可能 ✓掛金の取扱い:法人なら全額を損金、個人事業主なら全額を必要経費に算入可能 ✓前納の取扱い:向こう1年間の掛金を最大240万円(= 20万円 × 12ヶ月)まで一括納付することが可能 |
例えば、掛金月額を20万円に設定して年間240万円の掛金を支払い、事業年度末に前納で240万円の掛金を支払うことで、1年間で最大480万円の損金を作ることができます。
税務・会計の悩みはお気軽にご連絡ください
電話・フォーム・LINE・Chatworkから選べます。
税務・会計の不安を今すぐ解決しましょう!
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
2.経営セーフティ共済のメリット
経営セーフティ共済のメリット(魅力)は大きく4つあります。
(1) 掛金の全額が損金に算入できる(節税効果)
最大の特徴は「掛金全額を経費にできる」ことです。
例えば、月20万円を掛金に充当すれば、年間240万円の損金算入となり、その分だけ法人税や所得税が減少します。
| (例1)法人で実行税率30%の場合 240万円 × 30% = 72万円の税負担軽減(例2)個人で所得が650万円(最も高い所得税率が20%+住民税率10%の場合 240万円 × 30% = 72万円の税負担軽減 |
(2) 取引先倒産時に無担保・無保証で資金借入が可能
掛金総額の10倍、最高8,000万円まで借入可能です。また、「無担保・無保証」で利用できるため、緊急時の資金繰りに強力な支えとなります。
(3) 解約手当金による資金準備ができる
40か月(3年4か月)以上掛け金を払い続ければ100%の解約手当金が返戻されます。中長期的に資金を積み立てる効果があり、将来の退職金や大規模修繕費の原資にも活用可能です。
(4) 金融機関に依存しない資金繰り対策になる
銀行融資に頼らずに資金調達が可能なため、資金調達方法の選択肢が広がり、リスク分散にもつながります。
3.経営セーフティ共済のデメリット・注意点
経営セーフティ共済はメリットの大きな制度ですが、デメリットを把握していないと逆効果になる可能性があります。
(1) 解約時に課税される(課税の繰り延べがされているだけ)
解約手当金は「益金」として課税対象になります。掛金の支払時には、あくまで課税が先送りされているだけであり、解約時には反面、税負担が発生する点に注意が必要です。
(2) 掛金納付が長期にわたるため資金拘束リスクがある
月額20万円を上限まで積み立てると、約3年半で800万円に達します。流動資金が固定化されるため、短期的な資金繰りが厳しい企業には不向きです。
(3) 予定より早い解約だと返戻率が低下する
12か月未満で解約すると掛捨てとなり、40か月未満では元本割れとなるため、上記(2)と同様に資金繰りが厳しい企業には不向きです。
(4) 令和6年10月税制改正による再加入時の損金制限
令和6年10月以降、任意解約後2年以内に再加入しても掛金が損金算入できなくなりました。従来のように安易な解約と再加入を繰り返すことはできなくなっていることから注意が必要です。
税制改正の詳細は以下の記事をご参照ください。
経営セーフティ共済の税制改正で解約後2年間は再加入しても経費にならない!
税務・会計の悩みはお気軽にご連絡ください
電話・フォーム・LINE・Chatworkから選べます。
税務・会計の不安を今すぐ解決しましょう!
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
4.返戻率(解約手当金)の仕組みとシミュレーション
返戻率は解約理由や加入期間で大きく変わります。
なお、経営セーフティ共済の返戻率については、次の記事もご参考になさってください。
経営セーフティ共済の返戻率・受取り時の税金等を詳しく解説!
(1) 解約理由
解約理由には下表のように3つの種類があります。
| ✓任意解約:共済契約者の自己都合による任意解除
✓みなし解約:個人事業主の死亡、会社等法人の解散、事業譲渡、会社等法人の分割による解除 ✓機構解約:共済契約者による機構からの強制解除 |
(2) 解約理由・掛金納付期間ごとの返戻率
| 掛金を納付した月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
| 1か月~11か月 | 0% | 0% | 0% |
| 12か月~23か月 | 80% | 85% | 75% |
| 24か月~29か月 | 85% | 90% | 80% |
| 30か月~35か月 | 90% | 95% | 85% |
| 36か月~39か月 | 95% | 100% | 90% |
| 40か月~ | 100% | 100% | 95% |
(3) 実際のシミュレーション例(掛金月20万円の場合)
| 掛金期間 | 累計掛金 | 返戻率 | 解約手当金 |
| 12か月
(1年) |
240万円 | 0% | 0円 |
| 36か月
(3年) |
720万円 | 80% | 576万円 |
| 40か月
(3年4カ月) |
800万円 | 100% | 800万円 |
(4) いつ解約すると有利か?経営者が押さえるべきポイント
| ✓40か月以上継続すること:
これが損をしない最低条件となります。 ✓赤字年度での解約: 解約金の益金計上を赤字で相殺することができます。 ✓退職金支給と同時に解約: 解約金の益金計上を退職金で相殺することができ、課税負担をコントロールすることができます。 |
5.経営セーフティ共済の会計処理
ここでは経営セーフティ共済の会計処理について、掛け金支払い時と解約手当金の受取り時のそれぞれの仕訳を確認します。
(1) 掛け金の支払い時
一般的な会計処理は次のいずれかを採用することが多いです。
| ① 共済掛金 or 保険積立金 ××× / 預金 (申告調整で減算処理)
② 支払保険料 ××× / 預金 (申告調整不要) |
①の方法は、決算書上は資産(投資その他の資産)に計上し、税務申告の段階で損金算入(費用計上)する方法です。これにより、決算書上も費用処理する②の方法に比べて、銀行に評価される決算になります。
(2) 解約手当金の受取り時
掛け金の支払い時に採用した会計処理に合わせて、次のいずれかの会計処理を採用することが多いです。
| ① 預金××× / 共済掛金 or 保険積立金 (申告調整で加算処理)
② 預金××× / 雑収入 or 特別利益 (申告調整不要) |
6.経営セーフティ共済の出口戦略
経営セーフティ共済では、解約時に課税されるというデメリットへの対策として、出口戦略を設計することが極めて重要です。
(1) 退職金や事業承継時に合わせて解約
出口戦略として、退職金の支払いに合わせて解約すれば、解約手当金の益金に退職金の損金を相殺でき、課税を最小化することができます。
(2) 赤字年度に合わせて解約
出口戦略として、赤字年度に合わせて解約すれば、解約手当金の益金に営業赤字を相殺でき、課税を最小化することができます。
(3) 小規模企業共済や生命保険との組み合わせで最適化
| 制度 | 対象 | 節税方法 |
| 経営セーフティ共済 | 法人 | 掛金全額が損金算入 |
| 小規模企業共済 | 個人 | 掛金全額が所得控除・退職所得課税 |
| 生命保険 | 法人/個人 | 契約形態により損金算入可 |
これらの中から複数の制度を組み合わせることで、法人税・所得税の両面で最適化が可能です。
(4) 税理士に相談すべきタイミングとポイント
経営セーフティ共済では、掛金の損金算入で一時的に節税ができても、出口戦略を誤れば一気に課税負担が増えてしまいます。そのため、解約や掛金増額の判断は税理士に相談することが重要です。
特に相談すべきタイミングとしては以下が挙げられます。
| ✓決算前(利益調整)
✓退職金設計時 ✓事業承継時 |
税理士に相談することで、節税と資金繰りに関して、最も有利な出口戦略を設計することが成功のカギとなります。
7.中小企業経営者・不動産オーナーにとっての活用方法
ここでは、中小企業経営者・不動産オーナーにとって、経営セーフティ共済を活用する具体的な方法や活用イメージを確認します。
(1) 取引先依存度が高い業種でのリスク対策
製造業や建設業など、取引先の倒産リスクが大きい業種で効果的です。
(2) 大規模修繕の資金準備に活用するケース
不動産オーナーは、修繕積立と節税を同時に実現可能です。
ただし、個人の不動産所得においては、掛金を経費にすることができません。
不動産オーナーに対する経営セーフティ共済の活用方法については、以下の記事をご参考になさってください。
不動産オーナー(法人)におすすめ!経営セーフティ共済で節税・大規模修繕への備えが可能!
(3) 経営者個人の資産形成と法人税対策のバランス
法人・個人の双方の制度を併用し、資金繰りを強化する戦略が有効です。
8.よくある質問(Q&A形式)
経営セーフティ共済について、よくある質問をQ&A形式で整理しました。
Q1.掛金はいくらから始められる?
A.月5,000円から掛けることが可能です。
Q2.解約は自由にできる?ペナルティはある?
A.解約は自由にできますが、12か月未満は掛捨てとなってしまいます。また、40か月以上の払い込みで元本割れはなくなります。
Q3.他の共済制度と併用できる?
A.小規模企業共済やiDeCoとの併用も可能です。
Q4.経営セーフティ共済を利用して資金を借りる場合の流れは?
A.中小機構に申請 → 審査 → 掛金の10倍まで借入可能(返済期間は5~7年)。
Q5.設立1期目の法人は経営セーフティ共済に加入できない?
A.引き続き1年以上事業を継続している必要があるため、設立1期目の法人は原則として、経営セーフティ共済に加入することはできません。ただし、個人事業として開業した事業を全部引き継いで法人成りし、個人事業主期間を含めて事業期間が1年以上である場合には加入することができます。
9.まとめ
経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、節税効果と資金繰りリスクへの備えを同時に実現できる、数少ない国の制度です。掛金全額を損金算入できることで、短期的には税負担を軽減し、長期的には資金準備や倒産リスク対策としても機能します。
ただし、解約時の課税や資金拘束リスクには注意が必要です。40か月以上の継続、赤字年度での解約、退職金や事業承継との連動など、出口戦略を設計することで最大の効果を発揮します。
制度の仕組みや税務上の扱いは複雑であり、誤った使い方をすると逆効果になる可能性もあります。実際に加入や解約を検討する際には、必ず税理士に相談し、自社に最適な活用プランを立てることをおすすめします。
なお、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループにご依頼いただければ、東京税理士協同組合を通して経営セーフティ共済の申込ができます。また、制度の最新動向を踏まえ、貴社の決算・資金繰りに沿った最適解もご提案しますので、ご興味等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
税務・会計の悩みはお気軽にご連絡ください
電話・フォーム・LINE・Chatworkから選べます。
税務・会計の不安を今すぐ解決しましょう!
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
を徹底解説!.png)