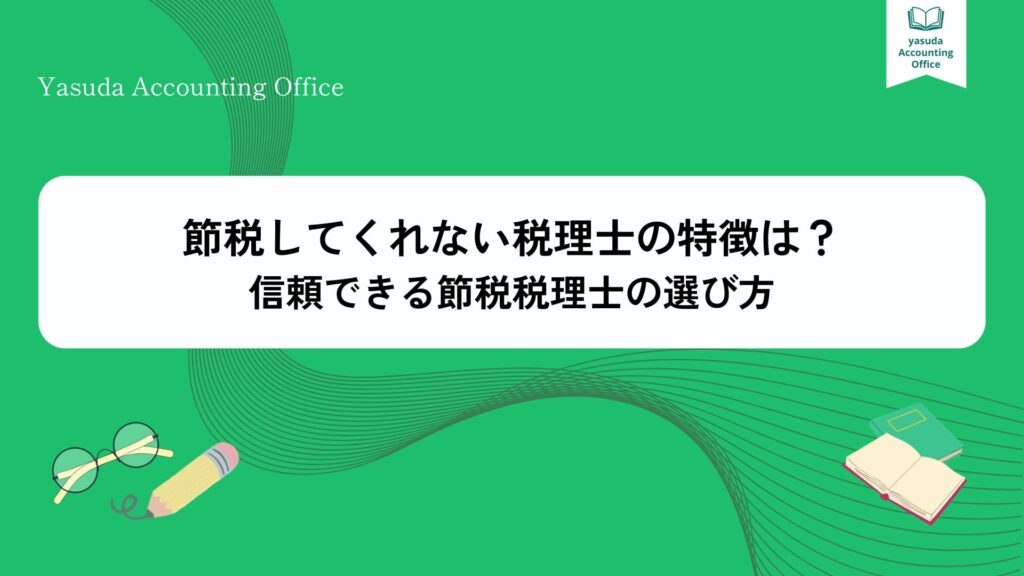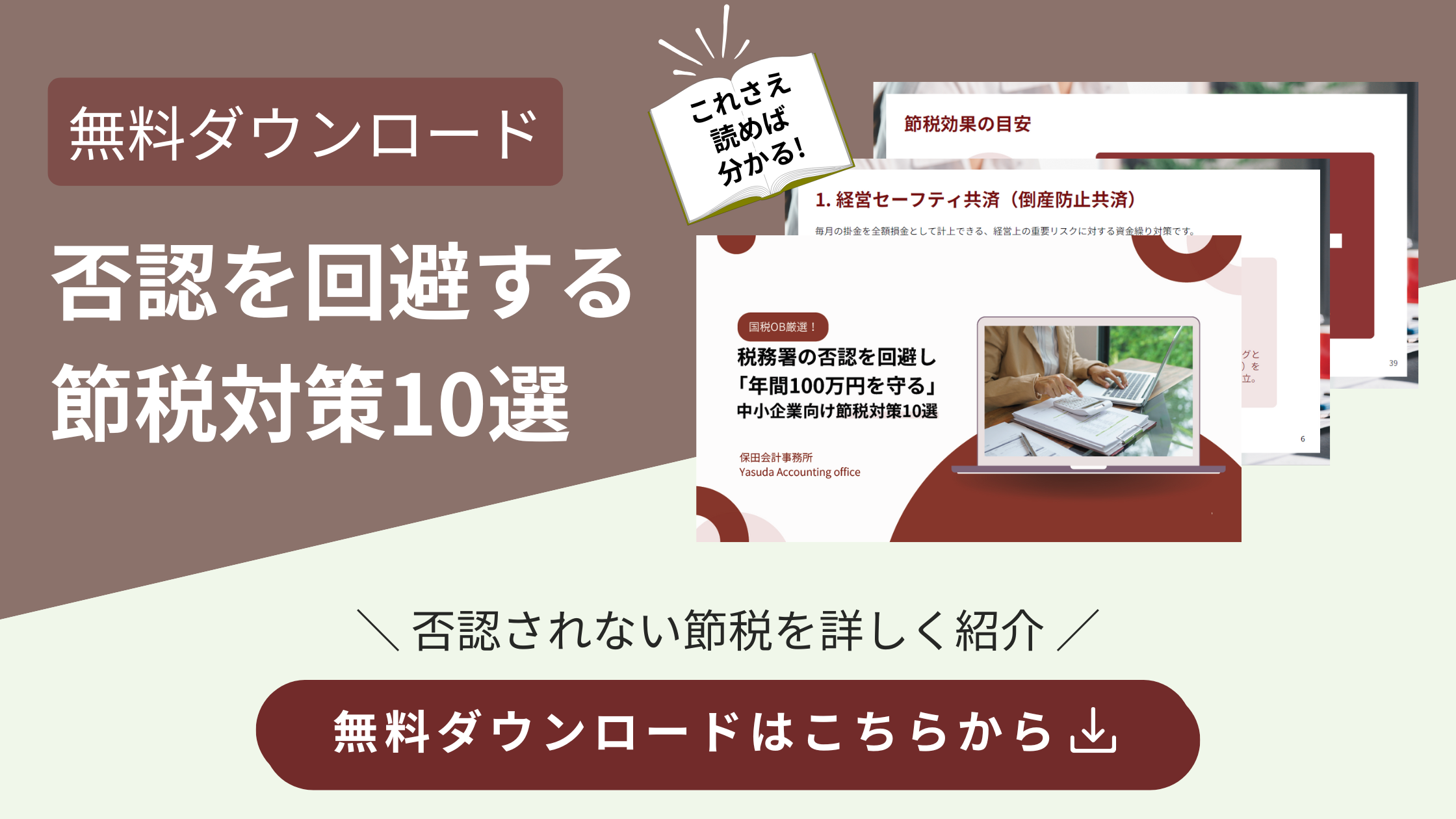税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
事業を続ける上で避けられないのが税金の負担です。
顧問税理士は本来、節税の提案をして経営を助ける存在ですが、「申告業務しかしてくれない」「節税に消極的だ」と感じる経営者も少なくありません。こうした税理士に任せてしまうと、余分な税金を払ったり、最新の税制改正を活かせず損をしたりする恐れがあります。
この記事では、節税してくれない税理士に共通する特徴と、その背景にある理由、節税対策が重要な理由、安心して任せられる税理士を見極めるための判断基準について解説します。
節税に強い税理士に、相談しませんか?
国税OB税理士が実践的な節税でキャッシュを守り、税務調査にも強い体制で伴走します。 Table of Contents
>保田会計事務所を詳しく知る<
節税してくれない税理士の特徴とは
顧問税理士に任せていても思ったような節税ができず、期待外れに感じてしまう経営者は少なくありません。その背景には、税理士側の考え方や対応姿勢にいくつかの特徴があります。
| 観点 | 節税してくれない税理士 | 信頼できる税理士 |
| 経営者理解 | ヒアリング不足、前年踏襲の申告のみ | 利益計画や将来像を踏まえた提案 |
| 節税スタンス | リスクを恐れすぎ、説明不足 | 法律に基づき明確に線引きして提案 |
| 税務調査対応 | 調査回避を優先し提案を抑制 | 根拠書類を整え、調査に耐えられる設計 |
| 情報更新 | 改正を追わず古い知識で対応 | 最新制度を理解し積極的に活用 |
| 契約内容 | 申告業務のみで提案は別料金 | 顧問料内に節税提案を含むケースが多い |
ここで紹介する内容に心当たりがある場合は、税理士の変更を検討するサインかもしれません。
→ 税理士の切り替えを検討している方はこちら
顧問先の要望を理解せず提案が少ない
経営者が本当に望んでいるのは「単なる申告」ではなく「手元資金を守るための具体策」です。しかし、一部の税理士は経営者の意向を十分にヒアリングせず、前年と同じ申告処理を繰り返すだけのケースがあります。
たとえば「今年は利益が増えそうだから税負担を抑えたい」といった声に応えるのではなく、無難に数字をまとめるだけ。結果的に節税のチャンスを逃し、顧問料を払っている意味を実感できない状況になりかねません。
節税と脱税の線引きがあいまいで消極的
節税は法律に沿った正しい方法であり、経営者にとっては当然の権利です。一方で脱税は違法行為であり罰則の対象になります。
しかし中にはその境界を明確に説明できず、リスクを恐れて必要以上に消極的な税理士もいます。本来なら合法的に認められた控除や特例を使えるのに、慎重すぎる判断で提案が行われないこともあります。結果として経営者は正当に減らせる税金を払い続けることになるのです。
税務調査リスクを恐れて提案を避ける
税務調査は経営者にとって負担になる出来事ですが、正しく処理をしていれば過度に恐れる必要はありません。それでも一部の税理士は「調査対象になったら困る」との理由で、挑戦的な節税提案を控えてしまいます。
例えば役員報酬の調整や経費の計上など、十分に根拠のある手法であっても避ける傾向があるのです。調査を恐れるあまり何もしないのではなく、調査に耐えられる正しい書類準備や根拠づけをサポートするのが本来の役割といえます。
最新の税制改正や節税スキームを学んでいない
税法は毎年のように改正が行われ、控除や特例の内容も変化します。例えば設備投資に関する優遇制度や中小企業向けの特別控除などは年度ごとに条件が異なります。
勉強を怠っている税理士では、こうした最新の制度を知らずに従来どおりの提案しかできません。その結果、本来なら税額を減らせるはずの方法を見逃してしまい、顧問先に不利益を与えることになります。常に情報をアップデートしているかどうかは、良い税理士を見分ける重要な基準です。
顧問料に節税提案が含まれていない
契約内容によっては、顧問料が「申告書の作成」や「会計処理の確認」に限定されており、節税提案は別料金となっていることがあります。その場合、経営者は追加費用を気にして相談しづらくなり、結果的に節税の機会を逃してしまいます。
顧問料が安いことを理由に契約したとしても、必要なサポートが含まれていなければ意味がありません。契約時に「どこまでがサービスに含まれるのか」を確認しておくことが大切です。
節税に強い税理士の特徴
ここでは節税に強い税理士の特徴を紹介します。
決算前に節税対策で法人税を抑えてくれる
節税に強い税理士は、決算が終わってからではなく、事前に対策を取る重要性を理解しています。決算の直前に利益を確認し、利益が大きく出ているなら法人税を抑えるための手段を検討します。ここで適切なアドバイスを受けられるかどうかで、支払う税額は大きく変わります。
役員報酬の見直しで法人税と所得税を調整
役員報酬は会社の利益と個人の所得に直結するため、設定金額によって法人税と所得税のバランスが変わります。例えば、報酬が少なすぎれば会社に利益が残りすぎて法人税が高くなり、逆に報酬を高く設定しすぎれば今度は個人の所得税が増えてしまいます。
節税に強い税理士は会社全体と役員個人の両方を見ながら、最も有利になる金額を一緒に検討してくれます。こうした調整は毎年の業績に応じて変える必要があり、専門家の判断が欠かせません。
設備投資や減価償却の活用で課税所得を圧縮
決算前に必要な設備を導入し、減価償却を計上することで課税所得を抑えることもよく使われる方法です。ただし何でも買えばよいわけではなく、事業に直結する資産であることが条件となります。
例えば、製造業なら機械設備、飲食業なら厨房機器など、事業の成長につながる投資が重要です。節税に強い税理士は「買ってよい設備」と「やめておいた方がよい投資」を見極め、長期的な経営にプラスになるようにアドバイスします。
税制改正に対応した最新の節税策を提案してくれる
税制改正は毎年行われ、特例や控除の条件は頻繁に変わります。節税に強い税理士はこれらの動きを常にチェックし、顧問先が不利にならないよう最新の情報を取り入れます。制度改正にいち早く対応できるかどうかで、使える優遇措置の数も大きく変わるのです。
中小企業向けの税制優遇制度を活用
中小企業には、研究開発費の控除や設備投資を支援する制度など、さまざまな優遇措置があります。しかし条件は複雑で、申請期限や対象となる資産の種類などを誤ると制度を使えなくなります。
節税に強い税理士はこれらの制度を熟知しており、会社に合った制度を選び、期限内に正しく活用できるように導いてくれます。結果として、本来よりも少ない税負担で成長のための資金を確保できます。
事業承継税制の改正を踏まえた相続税対策
中小企業の経営者にとって大きな課題となるのが事業承継です。後継者に株式や資産を引き継ぐ際には相続税や贈与税がかかりますが、事業承継税制を利用すれば大幅に負担を軽くできます。
ただし制度は改正が多く、条件が細かいため、専門家でなければ正しく活用できません。節税に強い税理士は最新の改正点を理解し、会社の状況や経営者の希望に合わせて最適な承継プランを立てます。これにより後継者が安心して事業を引き継ぎ、経営を安定させることが可能になります。
節税に強い税理士を選ぶポイントと見極め方
税理士選びは会社の未来に直結する大切な判断です。節税に強い税理士を見極めるには、契約前の初回相談や面談でどんな質問をし、どんな対応をしてくれるかを確認することが効果的です。ここでは相談の際に注目すべきポイントを紹介します。
税務調査に対する考え方を聞いてみる
税務調査への対応力は節税税理士の実力を測る大きな目安です。
単に「節税できます」と言うだけでなく、調査が入った場合にどう備えるのか、書面添付制度を利用しているかなどを質問すると、その税理士がどの程度リスクをコントロールできるかがわかります。安心して任せられるかどうかは、この答えで見極めやすくなります。
最新の税制改正への対応を聞いてみる
税制は毎年のように変わるため、最新の改正にどう対応しているかを尋ねるのも重要です。
例えば「令和6年度の税制改正で顧問先に影響がある内容は何か」と聞いたときに、具体的に説明できる税理士は知識を常に更新しています。逆に曖昧な答えしか返ってこない場合は、節税に強いとは言えないでしょう。
顧問料と節税効果の関係を確認する
料金の安さだけで判断せず、顧問料と節税効果のバランスを必ず確認しましょう。
初回相談のときに「顧問料にどこまでのサポートが含まれているのか」「節税提案は別料金になるのか」を質問してみると安心です。わかりやすく説明し、費用対効果を意識している税理士なら信頼できます。
自社の業種や規模に合った提案があるかを確かめる
業種や会社の規模によって使える制度や節税の方法は大きく変わります。
初回相談の際に自社の状況を伝えたとき、具体的な事例や制度を挙げて説明してくれる税理士は信頼できます。もしどの会社にも通用する一般的な答えしか返ってこない場合は、その税理士が本当に自社に合っているか疑問が残ります。
節税対策が重要な理由
節税対策というと、「税金を減らすためのテクニック」と考えられがちですが、本来は事業を安定させ、将来の選択肢を広げるための重要な経営判断です。
ここでは、なぜ節税対策が経営において重要なのか、その理由を整理していきます。
手元資金を確保し事業の安定につなげるため
節税対策は、単に税金を減らすことを目的としたものではありません。事業を安定的に継続するためには、売上や利益だけでなく、手元にどれだけ資金が残るかが重要になります。
必要以上に税金を支払ってしまうと、手元資金が減少し、資金繰りや投資判断に直接影響を及ぼします。節税によって確保できた資金は、運転資金としてだけでなく、設備投資や人材採用、事業拡大のための原資として活用することができます。
環境の変化や不測の事態に備えるため
事業環境は常に一定ではありません。売上の変動や景気の影響、取引先の状況によって、利益が大きく変動することもあります。
こうした状況の中で、税金の負担を適切にコントロールできていないと、黒字であっても資金不足に陥るリスクが高まります。節税対策は、予期せぬ事態に備えるためのリスク管理という側面も持っています。
経営状況を見直すきっかけになるため
節税を意識することで、税金や経費、利益の構造を改めて見直すきっかけが生まれます。どの税金に、どれだけ支払っているのかを把握することは、経営状況を正しく理解することにつながります。
数字を把握し、税負担の仕組みを理解することで、無駄な支出や改善点に気づきやすくなり、経営判断の精度も高まります。節税対策は、経営全体を見直すための入口とも言えるでしょう。
節税は自分でできる?税理士に頼むべき?
節税というと、「書籍やネットで調べれば自分でもできるのでは?」と考える経営者や個人事業主は少なくありません。
確かに日常的な経費の整理や領収書の保存、少額備品の処理方法など、基本的な部分であれば自分でも対応可能です。たとえば、30万円未満の備品を購入したときに特例を利用して一括経費処理するなど、知識さえあればすぐに実践できる節税手法も存在します。こうした“身近でシンプルな節税”は、自ら学び実行することで十分な効果を得られるケースもあるでしょう。
しかし、税制は毎年のように改正され、法人税・所得税・消費税・相続税といった幅広い分野で条件や期限が細かく定められています。最新の制度を常にキャッチアップし、適用要件を正しく理解したうえで実行するのは、専門知識のない経営者にとって容易ではありません。誤った解釈で処理を進めてしまうと、後の税務調査で否認され、追徴課税や加算税を課されるリスクさえあるのです。
自分でできる節税の限界とリスク
自分でできる節税には、明確な限界があります。
日常的な経費処理や基本的な控除であれば対応できますが、決算前の利益圧縮や役員報酬の調整、研究開発費控除や賃上げ促進税制といった複雑な制度の活用となると、自力で正確に運用するのは極めて難しいといえます。
特に、届出や証明書類の提出期限を一日でも過ぎてしまえば適用できない制度も多く、「知っていたけど間に合わなかった」という事態が起こりやすいのです。
また、制度ごとに「この資産は対象になるのか」「この支出は控除に含めてよいのか」といった判断を求められる場面が数多くあります。こうした線引きは国税庁の通達や判例にも関わる専門的な領域であり、自己判断では誤りやグレーゾーンに踏み込んでしまうリスクが高まります。
税務調査リスクを避けるなら専門家に任せる
税理士に相談する最大のメリットは、「安心して節税を進められること」です。最新の税制改正を踏まえた上で、会社の業績や事業計画に即した具体的な施策を提案してもらえるため、使える制度を取りこぼす心配がありません。さらに、節税の根拠を文書で整理し、税務調査に耐えられる形に仕上げてくれる点も大きな価値です。
たとえば、役員報酬の設定は法人税と所得税の両方に影響し、さらに社会保険料にも直結するため、最適化には高度な計算が必要です。これを自力で行うのは現実的ではありませんが、税理士であればシミュレーションを提示しながら最も有利な設定を一緒に検討できます。
また、事業承継や相続税対策のように数年単位で設計が必要な領域では、専門的なアドバイスがなければ大きな損失につながりかねません。経験豊富な税理士と早期に相談することで、長期的な経営の安定にもつながります。
顧問料はコストか?それとも投資か?
「税理士に頼むと顧問料がかかるから…」とためらう方もいますが、実際には顧問料以上の節税効果を得られるケースが多いのが実情です。適切な制度を活用することで数十万円から数百万円単位の税額軽減につながることもあり、その差額を考えれば顧問料はコストではなく投資といえるでしょう。
さらに、税理士に任せることで経営者自身が本業に集中できるという効果も。節税のために税法を調べ、書類を作成し、制度の要件を精査する時間を、事業に充てられるのです。
迷ったらまず初回相談で判断する
節税には自分でできる部分もありますが、制度の複雑化や税務調査リスクを考えれば、専門家に任せることで得られる安心と効果は非常に大きいといえます。特に決算前や設備投資・賃上げを予定している場合は、早めに税理士に相談することで選べる手段が格段に広がります。
「本当に税理士に頼むべきか」と迷っているなら、まずは初回相談を受けてみるのがおすすめです。相談を通じて、どのような提案をしてくれるのか、調査対応まで含めて安心できるかどうかを判断できます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
税理士を雇うメリットと費用相場は?失敗しないタイミングと選び方
節税にお困りの方は保田会計事務所にご相談ください
節税は会社や個人事業の資金を守り、安定した経営を続けるために欠かせない取り組みです。しかし、自分だけで正しく進めるには限界があり、法律や制度を熟知した税理士のサポートを受けることが安心につながります。
保田会計事務所では、豊富な実績と最新の税制に基づく専門的な知識をもとに、経営者一人ひとりの状況に合わせた節税対策を提案しています。法人税や所得税の調整から事業承継に関するご相談まで、幅広くサポート可能です。無理のない合法的な方法で税金を抑えたい、安心して経営に専念したいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
よくある疑問
節税相談は違法ではないのですか?
節税は法律に基づいた正当な方法であり、違法ではありません。
国が認めている控除や優遇制度を使って税金を減らす行為なので安心して相談できます。違法になるのは、売上を隠したり架空の経費を計上したりする脱税行為です。正しい根拠を持った節税であれば問題はなく、むしろ経営者が当然行うべき対策です。
税理士に頼むと費用はどのくらいかかりますか?
費用は依頼内容や会社の規模によって異なりますが、一般的に毎月の顧問料は数万円から十数万円程度です。さらに決算申告の時期には追加費用が発生することもあります。
個人事業主であれば年間数十万円以内に収まるケースが多く、中小企業では業務量に応じて高くなる場合もあります。ただし顧問料が多少高くても、提案によって大きく節税できれば結果的に負担は軽くなります。
税理士が嫌がる顧客とはどんな人ですか?
税理士は信頼関係を前提に業務を行うため、協力的でない顧客は敬遠されがちです。
例えば必要な書類を期限までに提出しなかったり、根拠を示しても過度な要求を繰り返したりする人は対応が難しいと感じられます。また顧問料を軽視して成果だけを求める態度も好まれません。円滑に業務を進めるためには、必要な情報を適切に伝え、税理士と二人三脚で進める姿勢が大切です。
決算直前でも間に合う節税策はありますか?
決算の3か月前からでも、賞与、在庫評価、投資時期の見直しで合法的に税額をコントロールできます。適用期限や証憑の要件があるため、購入・契約の前にご相談ください。