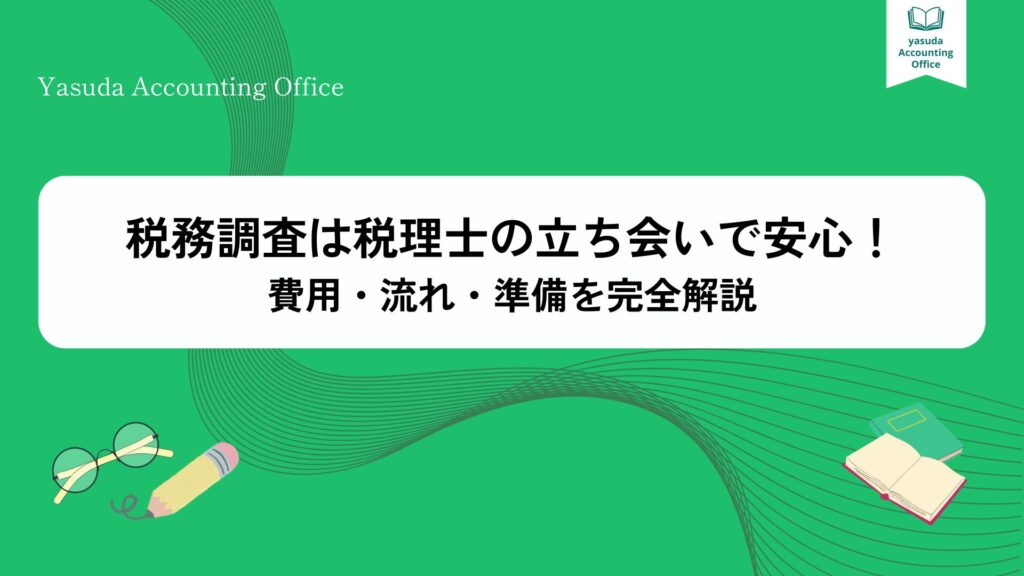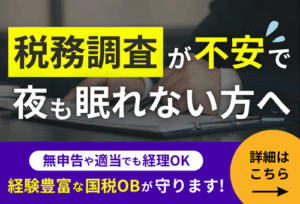税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
税務調査は、申告内容が適正かどうかを確認するために行われる制度上の手続きです。
正しく対処すれば大きな問題にはなりませんが、対応を誤ると追徴課税や重加算税といった思わぬ負担が発生する可能性もあります。そのため、冷静かつ慎重な準備が求められます。
とくに重要なのが、税理士による「立会い」の有無です。調査の現場では、税務署の調査官と対等にやり取りを行える専門家の存在が、調査の方向性を大きく左右します。税法に精通した税理士が同席することで、事実関係の誤認を防ぎ、適切な対応が可能となります。
本記事では、税務調査の基本的な種類や流れをはじめ、税理士に立ち会いを依頼する具体的なメリット、準備すべき資料、費用の目安、そして調査を円滑に終えるためのポイントについて詳しく解説します。
Table of Contents
税務調査とは?納税者の申告が正しいかどうかを確認する手続き
税務調査とは、税務署や国税局が、納税者の申告内容に誤りや不正がないかを確認するために実施する行政手続きです。調査は、過去に提出した確定申告書や帳簿書類などをもとに、売上や経費、利益の内容が正確であるかどうかを検証する目的で行われます。
すべての納税者に対して調査が行われるわけではありませんが、税務署が「申告内容に疑問がある」「調査対象として優先度が高い」と判断した場合に実施される傾向があります。
税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査(犯則調査)」の2種類があります。
任意調査
任意調査とは、納税者の協力を前提として行われる一般的な税務調査のことを指します。多くの場合、事前に税務署から電話や書面によって調査の通知があり、調査日や場所、調査の対象期間などについて納税者と調整した上で実施されます。
実際の調査では、税務署の担当官が会社や自宅などに訪問し、帳簿、領収書、請求書などを確認しながら、必要に応じて質疑応答が行われます。調査にあたっては、調査官が質問する内容や調査の進め方について、法令上の義務が強制されているわけではなく、あくまで納税者の任意協力のもとで進行します。
とはいえ、調査を拒否したり、曖昧な対応を取ったりすることで、税務署からの印象を悪化させる可能性もあるため、専門家の助言を受けながら適切に対応することが求められます。
強制調査(犯則調査)
一方、強制調査(犯則調査)は、悪質な脱税が疑われる場合に実施される、より厳格な調査手続きです。この調査は、国税局査察部、いわゆる「マルサ」が担当し、裁判所の令状に基づいて行われます。任意調査とは異なり、納税者の同意がなくても、帳簿やパソコンデータの押収、立ち入り、関係者への事情聴取などが強制的に実施される点が大きな特徴です。
対象となるのは、虚偽の帳簿作成、架空取引の計上、無申告による悪質な所得隠しなど、刑事罰の対象となりうる行為が疑われるケースです。強制調査の結果、重大な脱税が確認されれば、検察への告発や刑事事件としての立件に至ることもあります。
通常の事業者がこのような調査を受ける可能性は低いものの、万が一、強制調査に至るような誤解や疑いを招かないよう、日頃からの正確な帳簿管理と適正申告が何より重要です。
税務調査の立ち会いに税理士は必要?依頼するメリット
税務調査では、調査官とのやり取りに税法の専門知識が求められる場面が多くあります。そのため、税理士の立会いがあるかどうかで、調査結果や対応の負担は大きく変わってきます。
ここでは、税理士に立会いを依頼することで得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
【税務調査の当日】税務調査官の主張に対し、税法面から論理的に回答してもらえる
税務調査の現場では、調査官が指摘した内容に対して、その場で回答を求められることがよくあります。たとえ指摘が事実と異なる場合でも、納税者自身が即座に反論したり、適切に説明したりすることは容易ではありません。
税務署の誤解を防ぎ、不要な追徴課税を回避できる
税理士が立ち会っていれば、調査官の指摘が法的に妥当かどうかをその場で確認し、税法に基づいた根拠ある説明を行うことができます。これにより、事実誤認や解釈の相違による不要な修正申告や追徴課税を未然に防ぐことが可能となります。
特に、税法には細かな解釈の違いが生じる場面が多く、調査官の見解にそのまま従うことで、本来不要であった税金まで支払うことになってしまうケースも珍しくありません。税理士が同席していれば、こうした不利益を避けるための交渉や説明を即座に行うことができます。
税務署との交渉経験が豊富な国税OB税理士は特に安心
税務調査においては、経験値のある税理士ほど現場での対応力に優れています。なかでも、元国税調査官である「国税OB税理士」は、調査の進め方や調査官の意図を熟知しているため、やり取りの中で適切なタイミングで発言し、調査を有利に進めることができます。
【税務調査の前】税務調査の事前準備がしっかりできる
税務調査は、調査当日の対応だけでなく、事前の準備が成否を分ける重要なポイントとなります。税理士に相談することで、調査官の関心を引きそうな取引や帳簿の確認をあらかじめ行うことができ、想定外の指摘を受けにくくなります。
想定質問リストで模擬対応できる
税務調査では、調査官からの質問にその場で正確に答えることが求められます。しかし、急な質問に対して即答するのは容易ではなく、答え方によっては誤解を招いたり、不利な判断につながる可能性もあります。
その点、税理士に依頼して「想定質問リスト」を事前に作成しておけば、よくある質問や過去の調査事例をもとに、あらかじめ回答の準備を整えることができます。さらに、模擬的な質疑応答を繰り返すことで、調査当日の流れや雰囲気をイメージしながらリハーサルを行うことができ、精神的な負担も軽減されます。
本番で慌てることなく、冷静かつ的確に対応するためには、このような準備が極めて有効です。
過去の指摘事例を踏まえた資料の整備が可能
税務署が重視するポイントや、これまでよく指摘されてきた項目には一定の傾向があります。とくに交際費、外注費、役員報酬などは、処理方法や記載内容によって判断が分かれやすく、調査で確認されやすい項目です。
税理士は、これまでの豊富な調査対応経験をもとに、指摘されやすい部分を把握しています。事前に帳簿や証憑を見直し、整理・整備しておくことで、調査官からの突発的な質問にも備えることができます。
このように、実務上のリスクを洗い出し、資料の準備を整えておくことで、調査時の指摘や修正申告の必要性を最小限に抑えることが可能になります。
税務調査(任意調査)の流れ
任意調査は、税務署の事前通知を受けて行われる、一般的な税務調査の形式です。納税者の協力を前提として進められ、通常は1日から数日間かけて実施されます。以下に、調査の主な流れを時系列でご紹介します。
1. 税務署からの事前通知
まずは税務署から、電話や文書で調査実施の通知が届きます。この際、調査対象の期間、調査日、調査場所、必要書類の概要などが伝えられます。突然の通知に驚くこともありますが、事前に準備できる時間があることが任意調査の特徴です。
2. 調査実施日の日程調整
通知を受けた後、税務署と調査実施日を調整します。繁忙期や営業上の都合などがある場合には、日程変更を相談することも可能です。この段階で、税理士と事前打ち合わせを行うのが理想的です。
3. 必要書類を揃える
指定された帳簿や資料の準備を進めます。売上帳、仕訳帳、総勘定元帳、領収書、請求書など、取引内容を裏付ける書類が中心となります。顧問税理士がいる場合は、内容に不備がないかを確認し、事前に想定される指摘への対応方針を確認しておくと安心です。
4. 調査当日
調査当日は、税務署の調査官が事業所(または自宅)を訪問し、資料確認や質疑応答を通じて実地調査が行われます。帳簿の整合性や取引の実態について、調査官の質問に対し納税者または税理士が説明を行います。
5. 税務署の指摘に対して回答する
調査の途中で、調査官から処理内容に関する確認や指摘が入ることがあります。税理士が同席していれば、税法上の根拠をもってその場で説明や反論を行うことができ、誤解や不利な判断を防ぐことが可能です。
6. 調査結果の通知
調査が終了すると、調査官から調査結果の概要が口頭で伝えられます。ここで修正の必要があるか、特に問題がなかったかといった判断が示されます。
7. 修正申告書の作成
調査結果を受け、修正が必要とされた場合には、対象となる年度の修正申告書を提出します。税理士が対応することで、正確な修正と必要書類の整備を迅速に行うことができます。
8. 追徴課税の納税と対応
修正申告の結果、追加の税額(追徴課税)が発生した場合は、指定された期限までに納付します。延滞税や加算税が加わることもあるため、早めの対応が求められます。税理士の助言を受けながら、今後の申告体制の見直しを図ることも大切です。
税務調査の際に揃えておくべき資料と注意点
税務調査を円滑に進めるためには、必要な資料を事前に正確に準備しておくことが不可欠です。 調査官は、申告内容と実際の取引が正しく一致しているかどうかを、証憑書類や帳簿などを通じて確認します。
資料の不備や説明の曖昧さがあると、思わぬ指摘や追加調査に発展するおそれがあります。そのため、日頃から資料の整備状況には十分に注意し、調査通知を受けた段階で早めに対応を始めることが大切です。
用意する資料とは?
税務調査で提出を求められる主な資料には、帳簿類・証憑類・契約書類・申告書類などが含まれます。具体的には、総勘定元帳、仕訳帳、売上帳、経費帳、領収書、請求書、注文書、納品書、雇用契約書など、取引の実態を裏付ける書類一式が対象です。
法人の場合は、法人税や消費税の申告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書なども確認対象となります。
顧問税理士がいる場合には、調査通知を受けた時点で早めに相談し、対象年度に応じて必要な書類の洗い出しと精査を進めることが重要です。
税務署が注目するポイント①整合性
調査官が重視するのは、証憑や帳簿が整っているかだけでなく、内容に矛盾や不備がないかどうかという点です。領収書や請求書などの書類は、取引先名・日付・金額が帳簿の記載内容と正確に一致しているかを確認し、原本を確実に保管しておきましょう。
継続的な業務委託や外注取引がある場合には、契約書や覚書などの根拠資料を提示できるよう準備しておくことも大切です。取引の実態を明確に説明できるかどうかが、調査官の信頼を得るカギとなります。
また、帳簿類についても記載内容の整合性が求められます。仕訳帳や元帳が申告書と一致しているか、記帳ミス・集計ミスがないか、取引内容が適切に分類されているかを確認しましょう。特に現金取引が多い事業や、手書き帳簿を利用している場合は、記録の信頼性がより厳しく問われます。第三者が見ても明確に判断できる状態にしておくことが理想です。
税務署が注目するポイント②交際費、外注費、旅費交通費、福利厚生費
税務調査では、交際費・外注費・旅費交通費・福利厚生費といった、使途の判断が分かれやすい経費科目が重点的に確認されます。これらの経費は、支出の内容や目的、関係者、証憑の有無が明確であるかどうかによって、必要経費として認められるか否かが判断されます。
たとえば、飲食費が交際費に該当するかどうかは、誰とどのような目的で行ったものか、取引の関連性があるかどうかが基準となります。外注費についても、実態のない取引であると判断された場合には、経費として認められないリスクがあるため、契約書や成果物、支払い証憑などをきちんと揃えておく必要があります。
これらの科目は、調査官が特に注目するポイントであり、細かい確認が入ることが多いため、事前にしっかりと整理しておくことが求められます。
税務調査の立ち会い費用は?スポット依頼でも対応できる?
税務調査に税理士の立会いを依頼する場合、気になるのが費用面です。顧問契約を結んでいる場合は、契約範囲内で対応してもらえることもありますが、契約がない場合や調査の内容によっては、スポット契約(単発依頼)での対応が必要になります。
税理士に税務調査への立会いを依頼する場合、その費用は日数・内容・対応範囲によって異なります。
顧問契約を結んでいる場合の費用
顧問契約を結んでいる場合、契約内容に応じて調査立会いが顧問料に含まれていることもあれば、別途料金となることもあります。
たとえば、月額顧問料が3万円〜5万円程度の事務所であれば、簡単な立会いや相談はその範囲内で対応してもらえるケースもあります。
ただし、税務調査への対応が契約外となっている場合や、対応に日数を要するケースでは、1日あたり5万円〜10万円程度の追加料金が発生するのが一般的です。また、調査の結果、修正申告書の提出が必要になった場合には、別途5万円〜30万円程度の費用がかかることがあります。
修正内容の複雑さや、申告年度の数などによって金額が異なります。
スポット契約で依頼する場合の費用
税理士との継続的な契約がない場合、スポット契約(単発依頼)で税務調査の立会いを依頼することができます。スポット契約では、調査当日の立会いに加え、事前の打ち合わせや必要書類の確認、事後の対応やアドバイスまでを含めたパッケージで対応するケースが多く見られます。
費用の相場は、一連の対応を含めて20万円〜100万円程度が一般的です。ただし、調査対応の日数が複数日にわたる場合や、調査の内容が複雑な場合は、それ以上の金額となることもあります。
スポット契約を利用する際は、対応内容と費用の内訳について事前にしっかりと打ち合わせを行い、見積もりや契約条件を明確にしておくことが重要です。
税務調査が決まったら?立ち会いまでにすること
税務調査は、企業にとって精神的にも実務的にも大きな負担を伴うものです。慣れない対応を一人で進めようとすると、不安や緊張からミスや不利な発言をしてしまう可能性もあります。
しかし、信頼できる税理士がいれば、調査前の準備から当日の立会い、調査後の対応までを一貫して任せることができ、安心して調査に臨むことが可能です。
通知を受けたら即税理士に相談しよう
税務調査の通知が届いたら、最初に行うべきことは税理士への相談です。通知書に記載された調査対象の期間や内容を共有し、想定される指摘や必要書類を早い段階で整理することで、冷静に準備を進めることができます。
顧問税理士がいる場合は、日常の経理状況を理解しているため、スムーズかつ的確な助言を受けられます。できるだけ早く連絡を取り、調査当日までに万全の体制を整えておくことが重要です。
安心して本業に集中しよう
税務調査に関するすべての対応を専門家に任せることで、経営者や担当者は日常業務に専念できる環境を確保できます。 「税務調査があるから業務が進まない」といった状態を避け、本業への集中を妨げない体制づくりができるでしょう。
税理士が調査の窓口となり、適切に対応してくれることで、精神的な不安も軽減されます。「税務調査が不安」ではなく、「税理士がついているから安心」と思える環境こそが、落ち着いて調査に臨むための最良の備えです。
事前準備・当日の立ち会い・事後対応すべてを任せよう
税理士に依頼すれば、調査前の資料確認や質問対策の準備、調査当日の立会い、調査後の修正申告や税務署とのやり取りまで、すべてを任せることができます。
調査官とのやり取りにおいても、税理士がその場で適切に対応することで、事実誤認や不必要な追徴課税のリスクを回避しやすくなります。また、修正申告が必要となった場合にも、内容を整理し、スムーズな対応が可能です。
税務調査の立ち会いに対応できる税理士なら保田会計事務所
税務調査への対応は、経験と専門性が問われる重要な場面です。調査官とのやり取りでは、法律や実務に基づいた的確な判断と対応力が求められ、対応を誤れば本来不要な指摘や追徴課税を招くおそれもあります。
保田会計事務所には、豊富な実績と最新の税務知識を備えた専門家が在籍しており、調査の立会いから事前準備・事後対応まで、一貫してサポート可能です。
特に、過去に数多くの税務調査に立ち会ってきた実績があるため、調査官が注目するポイントや、指摘されやすい項目を事前に想定し、調査本番で慌てることのない万全な準備を行うことができます。
また、税務署との交渉においても、冷静かつ法的根拠に基づいた対応が可能なため、不当な指摘や不利益な処理を回避するうえで心強い存在です。
税務調査に不安を感じている方、これから通知を受けた方は、ぜひ一度保田会計事務所にご相談ください。
税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
・無申告、適当経理や領収書の廃棄もOK
・国税OBによる調査立会で徹底的に交渉
・税務署対応をすべて代行
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし