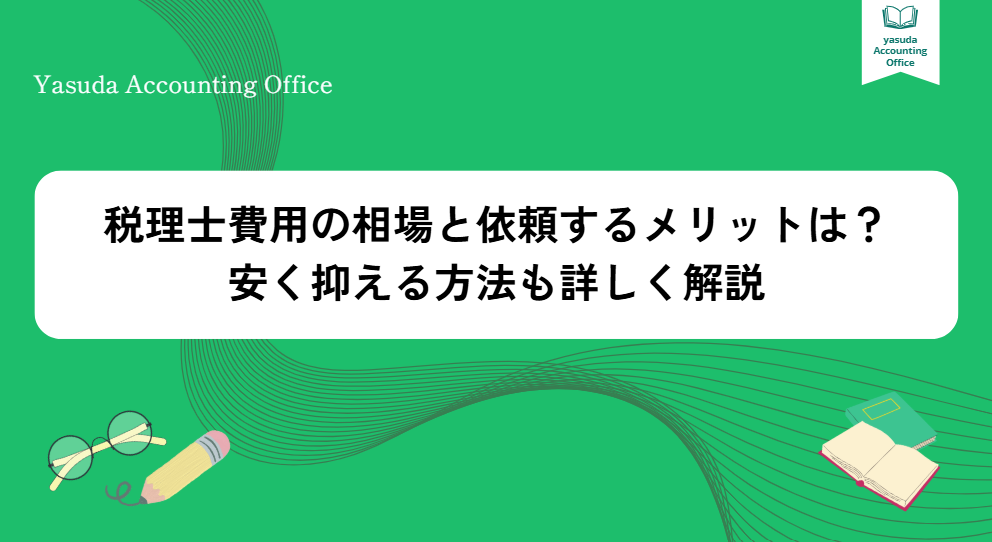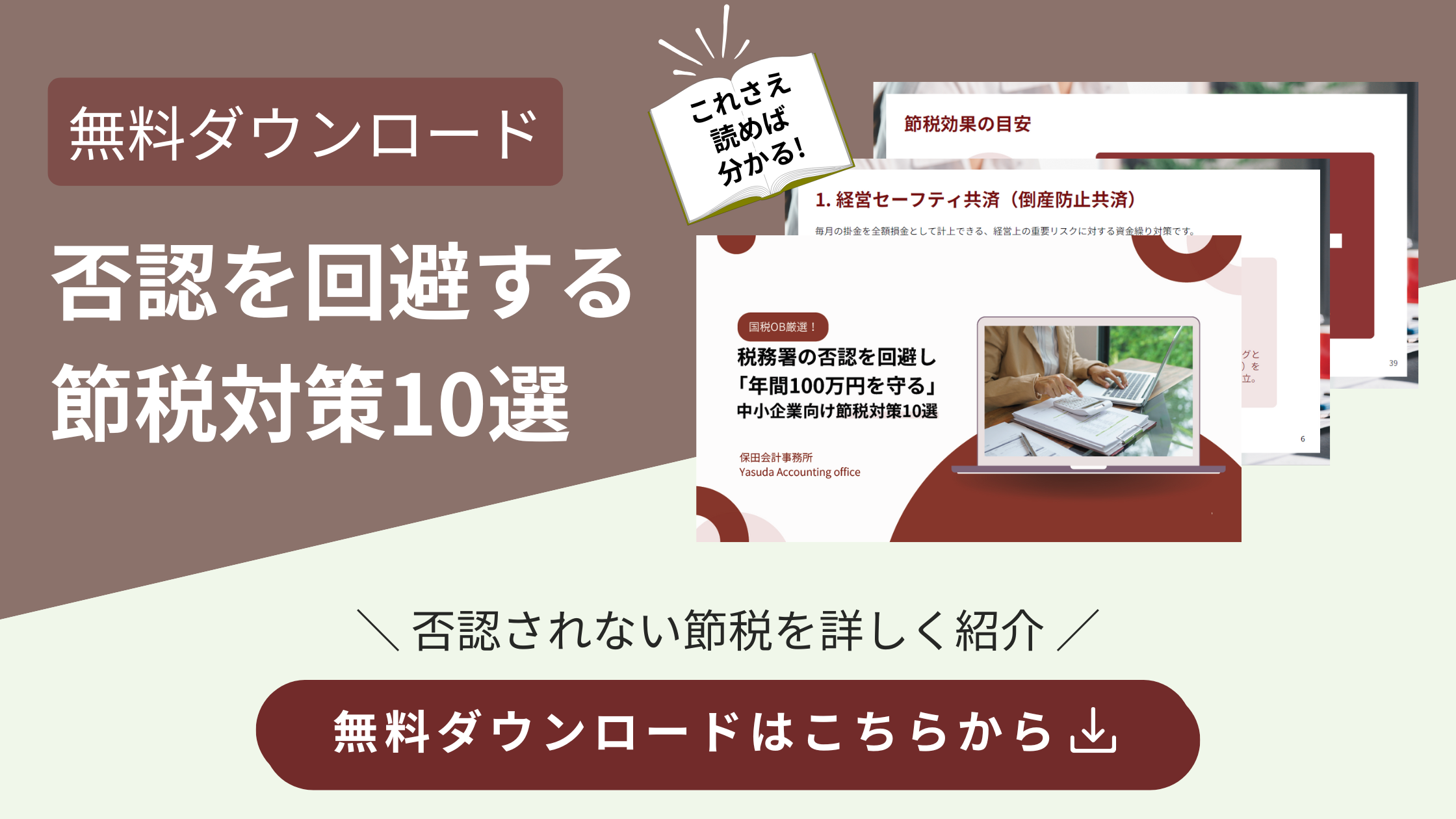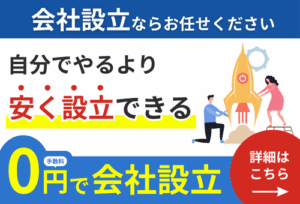税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
「税理士の費用はどれくらいかかるのだろう?」
「この金額は相場より高い?安い?」
「税理士費用を節約する方法はある?」
税理士を利用する際、まず費用を気にするという方は多いと思います。
一般的には、確定申告は5万円〜、法人の顧問契約であれば月額2万円〜が相場と言われています。
しかし、業務内容や依頼範囲によって大きく異なるため、税理士に依頼する際、費用の相場やサービス内容を知らないと、適正価格かどうか判断できないでしょう。
逆に適切な税理士を選べば、コスト以上のメリットを得ることも可能です。
本記事では、税理士費用の相場を中心に、費用の基本情報、適正な税理士費用の見極め方、料金を抑える方法まで詳しく解説します。
保田会計事務所では、税務に関するサービスを提供しています。ご興味のある方は下記URLをご覧ください。
保田会計事務所|江東区の税理士|経営者のための税務アドバイザリー
Table of Contents
税理士費用の基本
まず、おさえておくべき税理士費用の基本を理解しましょう。
ポイントとなる税理士報酬の基本の考え方は、「売上高」と「作業量」になります。
なぜ差があるのか?「売上高」と「作業量」
税理士費用は、業務内容・依頼範囲・地域・税理士の経験や専門性によって異なります。
例えば、個人の確定申告なら数万円でも、法人の顧問契約なら年間30万円〜100万円以上になることもあります。
売り上げが大きいほど税理士の作業量は増え、取り扱う税金も多くなるので「売上高」は報酬基準になります。
年間の売上が500万円以下か、500万円超1,000万円以下か、1,000万円以上かの部分で基準を設けている税理士事務所もあります。
一方、相続税の申告や税務調査の対応、依頼の難易度など、専門性が高い業務も費用は高額になります。これは、必然的に税理士の作業量や作業時間が増えますので、分かりやすいかと思います。
税理士にかかる費用の内訳
税理士に依頼する際の費用は、顧問料・各種作業料金・オプション費用に分かれます。
顧問料は毎月発生する費用で、税理士の訪問や税務署の監査立ち会いなど、事務所ごとにサービス内容が異なります。ただし、「年に一度の税務申告のみ依頼する場合は顧問料がかからない」契約も可能です。
各種作業料金には、記帳代行、確定申告、年末調整の代行費用などが含まれ、顧問料とは別途請求されるケースが多いです。
さらに、各種届出の作成やコンサルティングなどのオプション費用を設定している事務所もあるため、依頼前に確認しておくことが重要です。
では、具体的な料金相場を見ていきましょう。
【個人向け】税理士費用の相場|確定申告や相続税の料金比較
個人事業主やフリーランスの確定申告を税理士に依頼する場合、業務内容によって費用が変わります。
個人向け税理士費用の相場(事業規模別)
個人事業主やフリーランスが税理士に依頼する際の費用は、「確定申告料」「記帳代行費用」「顧問契約料」などに分かれます。
以下の表に、事業規模ごとの一般的な相場をまとめました。
| 事業規模(売上目安) | 確定申告料(年1回) | 記帳代行費用(月額) | 顧問契約料(月額) |
| 100万円未満(副業・小規模) | 3万円〜7万円 | 5,000円〜1万円 | なし〜1万円 |
| 1,000万円未満(個人事業主) | 5万円〜10万円 | 5,000円〜2万円 | 1万円〜3万円 |
| 1,000万円以上(青色申告・法人成り検討レベル) | 10万円〜20万円 | 1万円〜3万円 | 2万円〜5万円 |
個人向け税理士費用の内訳
確定申告料:年に一度の確定申告書作成(白色・青色申告対応)
記帳代行費用:会計ソフトへの入力・領収書整理などの代行
顧問契約料:税務相談・節税アドバイス・確定申告サポート
その他の費用(オプション):年末調整、節税対策、税務調査対応など
青色申告(最大65万円控除)を活用すると、税理士費用の元が取れることもあります。
また、クラウド会計ソフトを活用すれば、税理士費用を抑えられますので、税理士に依頼するところはしっかりと依頼し、それぞれ必要な個所で適切に活用しましょう。
相続税申告の税理士費用(遺産額別の相場)
相続税の申告は、遺産の総額によって税理士費用が異なります。
- 遺産5,000万円以下:40万円〜80万円
- 遺産1億円以下:70万円〜140万円
- 遺産3億円以上:120万円以上
相続税申告はミスするとペナルティが発生するため、税理士に依頼するのが安心です。
また、税務調査リスクを減らすため、相続専門の税理士を選ぶのがおすすめです。
🔗参考:相続プロ-相続税の税理士費用
【法人向け】税理士費用の相場|顧問契約の料金比較
法人が税理士と契約する場合、毎月の顧問料+決算申告費用がかかります。
法人の税理士顧問料の相場(売上規模別)
法人が税理士に依頼する際の費用は、「月額顧問料」「決算申告料」「記帳代行費用」「オプション費用」などに分かれます。
以下の表に、売上規模ごとの一般的な相場をまとめました。
| 売上規模 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 記帳代行費用 |
| 1,000万円未満(小規模法人) | 2万円〜5万円 | 10万円〜20万円 | 5,000円〜3万円 |
| 1億円未満(中小企業) | 5万円〜10万円 | 20万円〜50万円 | 1万円〜5万円 |
| 3億円以上(中堅企業) | 10万円〜30万円 | 50万円〜100万円 | 3万円〜10万円 |
法人の税理士費用の内訳
月額顧問料:税務相談・帳簿チェック・節税アドバイスなど
決算申告料:年に一度の決算書作成・法人税申告の手続き
記帳代行費用:会計ソフトへの入力や仕訳の代行
その他の費用(オプション):給与計算、年末調整、税務調査対応など
法人の税理士費用は、売上規模や業務内容によって大きく変わるため、事前にサービス内容を確認することが重要です。
保田会計グループの基準報酬は以下でご確認いただけます。
当事務所の基準報酬
適正な税理士費用の見極め方
税理士に依頼する際、料金が高すぎないか?サービス内容は適切か?適正な報酬かどうか確認します。以下のポイントを押さえて見極めましょう。
①相場と比較する(業務内容ごとの目安)
税理士報酬は、業務内容や依頼範囲によって大きく異なります。一般的な相場を知ることで、高すぎる・安すぎる料金を判断できます。
確定申告(個人事業主・フリーランス)
・確定申告のみ(記帳なし):5万円〜10万円
・記帳代行+確定申告:10万円〜20万円
法人の顧問契約
・小規模法人(売上1,000万円未満):月額2万円〜5万円
・中小企業(売上1億円未満):月額5万円〜10万円
相続税申告
・遺産5,000万円以下:40万円〜80万円
・遺産1億円以下:70万円〜140万円
相場より極端に高い場合は、他社と比較してサービス内容を確認しましょう。
②料金体系が明確かを確認する
税理士報酬は「月額顧問料」「決算申告費用」「追加オプション」などに分かれます。料金表が不明瞭な場合や、後から追加費用が発生する場合は要注意です。
事前に見積もりをもらい、総額を確認する、「記帳代行込み」や「決算申告は別料金」など、サービス範囲をチェックするなどしましょう。
③サービス内容と価格が見合っているか
同じ金額でも、税理士によって提供するサービスの質や範囲が異なります。
節税対策のアドバイスがあるか?
税務調査対応や経営相談も含まれているか?
対応のスピードやサポート体制は十分か?
「安いけど対応が遅い」「高いのにアドバイスがない」など、費用とサービスのバランスを考慮しましょう!
④複数の税理士から見積もりを取る
適正価格を見極めるために、最低でも2〜3社の税理士から見積もりを取得し、比較することが大切です。
無料相談を活用し、サービス内容・料金を直接確認する
実績や口コミをチェックし、信頼できる税理士かを見極める
「初回無料相談」を実施している税理士を選ぶと、費用対効果を判断しやすいのでおすすめです。
全般を通して、「安さ」だけで選ぶのではなく、「コスト以上の価値を提供してくれる税理士」を選ぶことが重要です。
税理士に確定申告を依頼したほうがよいケース
税理士に依頼すると、確定申告がスムーズになるだけでなく、節税対策や税務リスクの軽減にもつながります。まずは、以下のようなケースでは、税理士に依頼するメリットが大きいでしょう。
①事業の売上や経費が多く、帳簿の管理が複雑な場合
取引が多く経理作業が負担になっている場合は、税理士に依頼することで業務の効率化が図れます。
自分で申告書を作成する必要がなくなり、業務の負担を軽減できますし、特に、帳簿作成・領収書整理・売掛金や買掛金の入力まで対応してもらうと、経理作業の手間を大幅に削減できます。
個人事業主やフリーランスにとって、本業の合間に経理や事務作業をこなすのは簡単ではありません。税理士に依頼すれば、時間を効率的に使いながら、正確な申告が可能になります。
②青色申告を活用して節税したい場合
青色申告は、個人事業主やフリーランスにとって最も効果的な節税方法の一つです。最大65万円の控除が受けられるほか、赤字の繰越しや家族への給与支払いを経費にできるなど、節税メリットが多くあります。
しかし、複式簿記の記帳が必要であり、仕訳や帳簿作成の手間が増えるため、税務知識がないと申告ミスのリスクも高まります。
特に、青色申告の要件を満たしていないと控除が適用されないケースもあるため、税理士に相談して正しく申告することが重要です。
③副業で年間20万円以上の所得がある場合
副業で年間20万円を超える所得があると、確定申告が必要になります。しかし、本業の給与と副業所得を合算して税金を計算する必要があるため、税額の計算や控除の適用が複雑になりがちです。副業の収入が増えるほど、税務申告の負担も大きくなるため、税理士に相談して適正な申告と節税を行うことが必要でしょう。
その他、住民税の申告方法を調整し、本業の会社に副業の影響が及ばないようアドバイスを受けられるというメリットもあります。
④不動産所得がある場合
不動産所得がある場合、確定申告が複雑になり、適切な節税対策が求められます。特に、減価償却費の計算や経費の仕訳など、正確な知識が必要な項目が多く、ミスをすると税務調査のリスクが高まります。
減価償却費や修繕費を適切に計上し節税に繋げたり、管理費・固定資産税・ローン利息・火災保険など、適切な経費を見極められます。また、不動産所得の種類ごとに最適な申告方法も選択できます。
⑤税務調査のリスクを避けたい場合
過去に税務調査を受けた経験がある方や、申告内容に不安がある方は、税理士に依頼することでリスクを軽減できます。
税理士は税務の専門家であり、正確で信頼性の高い確定申告をサポートしてくれます。所得税の確定申告では自己申告した内容をもとに税額が決まるため、ミスなく計算し申告することが重要です。
税理士に任せることで、記入ミスや控除の適用漏れを防ぎ、抜けのない確定申告書や決算書を作成できます。また、税理士が関与することで、税務署からも正確な申告として認識されやすくなるというメリットもあります。
⑥番外編:税務調査の際に対応してもらえる場合がある
個人事業主の規模に関係なく、税務調査の対象になる可能性はゼロではありません。税理士に確定申告や記帳を依頼していると、税務調査が入った際に税理士が対応してくれるケースもあるため、安心して任せることができます。
ただし、税務調査の対応は別途料金やサポートが含まれない場合もあります。依頼前に、税務調査対応が可能かどうか、追加費用の有無を確認しておきましょう。
税理士費用を安く抑える3つの方法
最後に、税理士費用を安く抑えるコツをご紹介します。
①クラウド会計ソフトを活用する
記帳代行を税理士に依頼せず、自分でクラウド会計ソフトを使えばコスト削減になります。
また、税理士とのデータ共有もスムーズになり、打ち合わせの時間も短縮できるメリットもあります。
②必要なサービスだけを依頼する
「確定申告のみ」「決算申告のみ」など、ピンポイントで依頼すると費用を抑えられます。
節税対策や経営相談が不要なら、顧問契約なしのスポット依頼がおすすめです。
③複数の税理士から見積もりを取る
税理士によって料金設定が異なるため、相見積もりを取ることで適正価格で依頼できます。
「初回無料相談」を活用し、料金とサービス内容を比較するのがポイントです。
税理士費用は高い?安い?費用対効果を考える
「税理士費用が高い」と感じる方も多いかもしれませんが、適切な節税アドバイスを受けることで、支払う税金を数十万〜数百万円削減できるケースもあります。
例えば
・税理士のアドバイスで役員報酬を最適化し、年間100万円の節税に成功!
・法人化のタイミングを見極め、所得税・住民税を大幅に削減!
など、成功事例は多数あるので、気になる疑問や悩みがあればぜひ税理士に相談してみてください。
税理士は、手間を減らしつつ、正しく節税できるのが最大のメリットです。
節税対策や税務リスク回避により、支払う税金を大幅に削減できる可能性があります。また、経理業務の負担が減り、本業に集中できるため、売上向上にもつながります。
税理士費用以上のメリットを得られるケースが多く、費用対効果は高いと言えるでしょう。
まとめ
税理士に依頼する際の費用が気になる方も多いと思いますが、アドバイスをうまく活用することで税理士費用以上のメリットが得られることがあります。税理士費用の相場を知り、最適な依頼方法を選んでみてください。
「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、節税や税務調査対応に力を入れており、国税OBからの実践的なアドバイスを提供しています。
また、既に顧問税理士がいる方のセカンドオピニオンも対応しております。
ご興味等ございましたら、いつでも以下のサイト内、フォーム入力やLINEでお気軽にご相談ください。