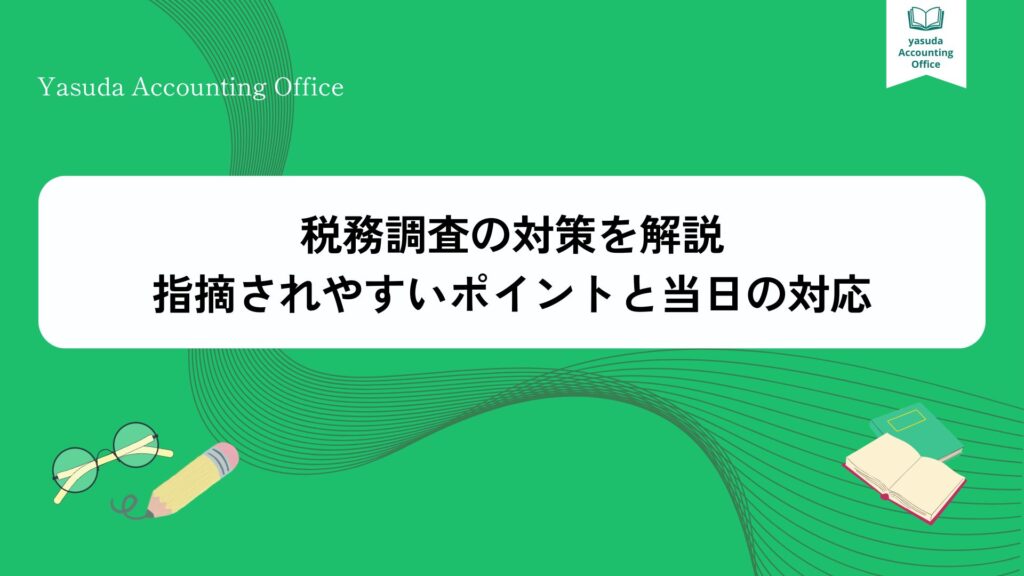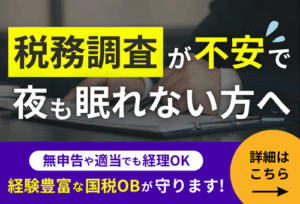税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
税務調査は、どの企業・個人にも起こり得る突発的なイベントです。「どこを見られるのか」「何を準備すべきなのか」が曖昧なまま当日を迎えると、必要以上に不安が高まってしまいます。
本記事では、税務調査で指摘されやすいポイントと、事前に整えておくべき対策、当日の対応方法までを専門家の視点で整理して解説します。
Table of Contents
税務調査とは?
税務調査とは、申告された税金の内容が正しいかどうかを税務署が確認する手続きです。法人だけでなく個人事業主にも実施され、特別な問題がなくても一定の頻度で行われる仕組みになっています。
調査の目的は、帳簿や書類が法律の基準に沿って作成されているか、また実際の取引内容を正しく反映しているかを確かめる点にあります。調査は、事前通知、当日の確認、調査後の整理という流れで進み、この全体像を理解しておくと、初めての方でも必要以上に不安を感じず落ち着いて対応できます。
この章では、税務調査の概要について解説します。
税務調査の方法
税務調査には「実地調査」と「机上調査(書面調査)」の二つがあります。
実地調査は調査官が会社や事務所に来訪し、その場で帳簿や証憑を確認する一般的な調査方法です。取引の背景を確認するため、担当者へ質問されることもあります。
一方、机上調査は、提出された申告書や資料を税務署内で確認する簡易的な調査で、特に相続税や贈与税ではこの形式が増えています。申告の整合性が確保されていれば、訪問調査に至らないこともあります。
どちらも目的は、申告内容が事実に基づいているかを確かめることです。
税務調査の権限
税務調査には、権限の異なる「任意調査」と「強制調査」という区分もあります。
任意調査は、ほとんどの法人や個人が受ける通常の税務調査を指し、調査官と日程調整をしたうえで、帳簿や書類を提示しながら進められます。調査官が強制的に資料を押収したり、自宅や事務所に無断で立ち入る性質のものではありません。
これに対して強制調査は、重大な脱税や不正の疑いがある場合に行われるもので、国税局査察部、いわゆる「マルサ」が担当します。裁判所の令状に基づき資料の押収が行われるなど、捜査的な性質が強く、一般の事業者が経験することは極めてまれです。多くの方が受けるのは任意調査であり、帳簿を整えておけば過度に恐れる必要はありません。
税務調査のスケジュール
税務調査のスケジュールは、大きく分けると「通知が来てから当日まで」「調査当日」「調査後」という三つの期間で考えると理解しやすくなります。
いつ、どのくらいの期間で、何をしておくべきかをつかんでおくと、必要以上に慌てずに準備を進められます。
| 時期 | 期間の目安 | 主な流れ・税務署側の動き | 納税者側でやることの例 |
| 事前通知〜調査当日まで | おおむね1〜3週間程度 | 税務署から電話や書面で調査日・担当者・対象期間などが通知される | 帳簿・証憑の整理、対象期間の確認、担当者や税理士との打ち合わせ |
| 調査当日 | 1日〜数日 | 調査官が来訪し、帳簿・証憑の確認、ヒアリング、現場確認などを行う | 必要資料の提示、取引内容の説明、追加資料の整理 |
| 調査当日終了後〜結論が出るまで | 数週間〜数か月程度になることも | 税務署側で論点整理、必要に応じて追加資料の依頼、是正の要否の検討 | 指摘内容の確認、追加資料の提出、修正申告が必要かどうかの検討・相談 |
事前通知
事前通知は主に電話で実施され、調査日までの期間は一般的に一〜三週間ほどの余裕があります。この間に、帳簿や証憑を確認し、通帳との照合や書類の整理を進めておくと、調査の進行が大きくスムーズになります。
また、社内で情報共有を行い、税理士が立ち会う場合は日程の調整や想定される質問の洗い出しも必要です。もし準備が間に合わないと感じた場合には、早めに税務署へ連絡し、日程変更の相談をすることも可能です。
調査当日
調査当日は、調査官の来訪から始まり、簡単なあいさつと当日の流れの確認が行われます。その後、午前中は帳簿や証憑を中心に確認が行われ、午後になると取引の背景や事業の実態について質問を受けることが一般的です。
会社の規模や取引内容によっては、一日で終わらず二日以上にわたる場合があります。初日は全体の流れを把握し、二日目以降は重点的に気になる取引を詳しく確認するという進め方が行われることが多くなります。
調査後
調査の全体確認が完了すると、その場で大まかな所見が伝えられます。その後、税務署内での整理作業が行われ、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。提出された資料を踏まえて、最終的に修正申告が必要かどうかが判断され、調査結果として伝えられます。
税務調査は当日の作業だけで終わるものではなく、通知から結論まで数週間から数か月ほどかかることもあります。全体のスケジュールを理解しておくことで、落ち着いて準備し、必要な対応を進めることができます。
税務調査で指摘されやすいポイント
この章では、税務調査で特に取り上げられやすい論点について、それぞれ詳しく解説します。
売上計上漏れ
売上計上漏れは、税務調査でもっとも指摘されやすい代表的な論点です。調査官は、売上が意図的またはミスによって少なく計上されていないかを確認するため、入金記録、請求書、通帳の動きなどを細かく突き合わせていきます。
典型的な例として、入金があるのに売上として計上されていないケース、前受金として処理されているものの実際には売上であるケース、売上計上日が月をまたいで不自然に後ろへずらされているケースなどがあります。
法人では月末処理のタイミングのズレ、個人事業者では現金売上の記録漏れが特に多く見られます。意図的な漏れではなく、担当者の処理ミスで指摘される例も多いため、日々の入金確認と売上計上の整合性を見直すことが大切です。
経費の私的利用と証拠不備
経費が本当に事業のための支出だったかどうかは、税務調査で必ず確認される項目です。特に、交際費、車両費、旅費交通費、消耗品費といった私的流用が疑われやすい費目は、調査官の着目点になりやすくなります。
調査官は、領収書の内容、支払先、金額だけでなく、その支出の背景を丁寧に確認します。説明が曖昧だったり、領収書の裏に目的が書かれていない場合には、事業関連性に疑問を持たれやすくなります。また、法人の支出と個人の支出が混じりやすい会社では、私的利用の疑いが強まりやすいため注意が必要です。
日頃から、どの支出がどの業務と関連しているかを簡単にメモしておくと、調査官の理解が早くなり、余計な質問を避けることができます。
交際費・福利厚生費
交際費と福利厚生費は名前が似ていて混同しやすいため、税務調査でも指摘されやすい項目です。交際費は取引先との関係を深めるための支出、福利厚生費は従業員のための支出という違いがあります。
例えば、従業員のみで行った食事会は福利厚生費として扱われますが、取引先が参加した場合は交際費に該当します。領収書に参加者名や目的を記載しておくことで、その支出がどちらに当たるか明確になり、調査時の誤解を防ぐことができます。
交際費は税務上の取り扱いに制限があるため、区分が曖昧な場合は調査官が重点的に確認する傾向があります。
名義預金
相続税の税務調査で多く取り上げられるのが名義預金です。名義預金とは、名義は子どもや配偶者でも、実際には亡くなった方(被相続人)が管理していた預金を指します。
調査官は、通帳の管理状況、入出金の流れ、生前に贈与の意思があったかどうか、預金を誰が自由に使っていたかなどを細かく確認します。名義と実態が一致していない場合、その預金は相続財産として扱われます。
また、生前贈与として認められるためには、贈与の意思の確認、受け取った側の管理などが求められます。贈与契約書がなく、これらが曖昧な場合には、申告漏れとして指摘されやすくなります。相続税調査は、生活費や資金移動まで細かく見られる点が特徴で、一般の税務調査とは着眼点が異なるため、専門家の助言が役立つ場面が多くあります。
税務調査の対策
この章では、税務調査の対策ポイントについて詳しく解説します。
帳簿・証憑を整理しておく
帳簿や証憑の整理は、税務調査に備えるうえで最も基本的で、かつ効果が大きい準備の一つです。調査官は、取引の記録とその裏付けとなる証憑がきちんと紐付いているかを重点的に確認します。
請求書や領収書、契約書などは日付ごと、または取引先ごとにまとめておくと、調査官から求められた資料をすぐに取り出すことができ、調査の進行が円滑になります。特に領収書については、支出の目的が分かりにくい場合が多いため、裏面に簡単なメモを記しておくと効果的です。
支出の背景が明確になっているだけで、調査官はその取引の業務関連性を理解しやすくなります。また、通帳の入出金と帳簿の内容が一致しているかを事前に確認しておくことで、調査当日の問い合わせが減り、不必要な混乱を避けられます。
税理士と相談しておく
税務調査の準備を進めるうえで、税理士への相談は非常に有効です。税理士は調査官がどのような視点で資料を確認するか、どのような点を疑問に思うかについて熟知しており、事前に整理しておくべき資料や注意点を的確に助言できます。
特に、外注費と給与の区分、役員報酬の扱い、経費の妥当性など、判断が分かれやすい論点については、税理士の見解が調査官の理解に影響することがあります。また、調査当日に税理士が立会うことで、質問の意図を正確に捉えたうえで回答ができるため、不利になる説明を避けることにもつながります。
さらに、調査官とのやり取りに不慣れな方にとっては、税理士の存在が精神的な支えとなり、落ち着いて対応できる環境を整える助けにもなります。
当日の立会者は必ず事前に決めておく
調査当日に最も重要なのは、調査官とやり取りを行う「窓口役」を明確にしておくことです。複数の担当者がその場で回答すると説明がぶれてしまい、調査官に不信感を与えてしまいます。
また、税理士が立ち会う場合は、事前に調査範囲や想定される質問を共有し、どのような方針で回答していくかを打ち合わせておくことが大切です。窓口が一貫していれば調査官が話を理解しやすく、調査全体が落ち着いた雰囲気の中で進行します。
調査官が嫌がる資料の出し方を避ける
調査官が最も困るのは、必要な書類がすぐに出てこない状況です。資料が散らばっていたり、どの書類がどの取引に対応しているか分かりにくい状態だと、帳簿管理が不十分だと判断され、調査が長引く可能性が高まります。
また、調査官に求められていない資料を大量に提示することも避けるべきです。関係のない書類を出してしまうと、余計な疑問を生むことがあり、結果として調査の範囲が広がりかねません。
必要なのは、調査官の質問に応じて、必要な資料だけを落ち着いて提示することです。目的に合った資料を過不足なく示せれば、調査官は確認作業を効率的に進めることができます。
曖昧な回答をしない
税務調査では、曖昧な回答や推測を含む説明はなるべく避ける必要があります。「覚えていません」「担当者が辞めたので分かりません」といった発言は、調査官に追加の確認を促してしまい、調査が長引く原因となります。ただし、記憶が曖昧なままで回答することは後々に大きな問題になりかねませんので、本当に分からないことや覚えていないことは中途半端に回答するのではなく「覚えていないので、調べてから回答します」「担当が別の者なので、担当者に確認してから回答します」といった回答をする方がいいです。
また、質問されていない内容まで自ら話してしまうと、意図しない論点に発展する可能性があります。調査官からの質問に対しては、事実だけを簡潔に伝えることが基本となります。落ち着いて事実を説明する姿勢が、調査官の信頼を得るために重要です。
税理士に相談するメリットは?
この章では、税理士に相談することで得られる具体的なメリットについて分かりやすく解説します。
調査官の着眼点を事前に理解できる
税理士は日常的に税務調査に立ち会っているため、調査官がどの資料を重視し、どの点を疑問に感じやすいのかを経験的に把握しています。
そのため、調査前の段階で「どこが論点になりやすいか」「説明を用意しておくべき部分はどこか」を明確にすることができ、効率的に準備を進められます。特に、経費の妥当性、外注費と給与の区分、売上計上のタイミングなど、実務上判断が分かれやすい部分は、税理士の視点が対策の精度を高めます。
調査当日に不利な説明を避けられる
税務調査中は、調査官の質問に対して適切に回答することが重要ですが、専門知識がない場合には余計なことを話してしまったり、意図しない誤解を招く説明をしてしまうことがあります。
税理士が同席していれば、質問の意図を補足しながら回答内容を整理できるため、不利な発言を避けることができ、調査官とのコミュニケーションも円滑になります。また、調査官が誤った理解に基づいて指摘を行った場合にも、その場で冷静に説明し、適切な修正を促すことができます。
事後対応まで一貫してサポートしてもらえる
税務調査は当日で終わりではなく、調査後の説明や修正申告の判断、改善提案など多くの作業が続きます。税理士は調査後の説明内容を整理し、判断が難しい論点について納税者が不利にならないよう支援します。
また、調査官の指摘に対して反論が必要な場合や、説明文書の作成が求められる場合にも、必要な根拠を示しながら適切な対応方針を提案することができます。こうした一連のサポートによって、調査の負担は大幅に軽減され、最終的な税負担のコントロールにもつながります。
精神的な負担を大きく軽減できる
税務調査は経験がない人にとって精神的な負担が大きく、緊張や不安から本来の説明ができなくなることがあります。
税理士がそばにいることで心理的な安心が生まれ、落ち着いて調査に臨むことができます。調査官とのやり取りも税理士がサポートしてくれるため、納税者が一人で抱え込む必要がなく、冷静に対応することができます。
お困りの方は保田会計事務所にご相談ください
税務調査の事前準備から当日対応まで一貫してサポート
保田会計事務所では、税務調査の事前準備段階から、必要な資料の整理方法、調査官が重視するポイント、想定される質問への回答方法などをきめ細かくサポートしています。
調査当日には担当税理士が立ち会い、調査官の質問意図を整理しながら、納税者が不利にならないよう適切な説明を行えるよう支援します。調査官とのやり取りに不慣れな方でも、安心して調査に臨むことができる環境を整えています。
調査後のフォローと改善提案も丁寧に実施
税務調査が終了した後も、その結果を整理し、必要に応じて修正申告や改善策の提案を行います。特に判断が難しい論点については、根拠に基づいた説明を行い、納税者が不利にならないよう最適な対応を一緒に検討します。
また、同じ論点で次回以降の調査が繰り返されないよう、内部体制の改善や経理処理の見直しについても実務的なアドバイスを提供します。
相続税・法人税・個人事業主まで幅広く対応可能
保田会計事務所では、法人税・消費税・源泉所得税の調査だけでなく、特に専門性の高い相続税や贈与税の税務調査にも多数の対応実績を持っています。
事業規模や業種を問わず、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行うため、初めての方でも安心して相談できる体制を整えています。
税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
・無申告、適当経理や領収書の廃棄もOK
・国税OBによる調査立会で徹底的に交渉
・税務署対応をすべて代行
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし