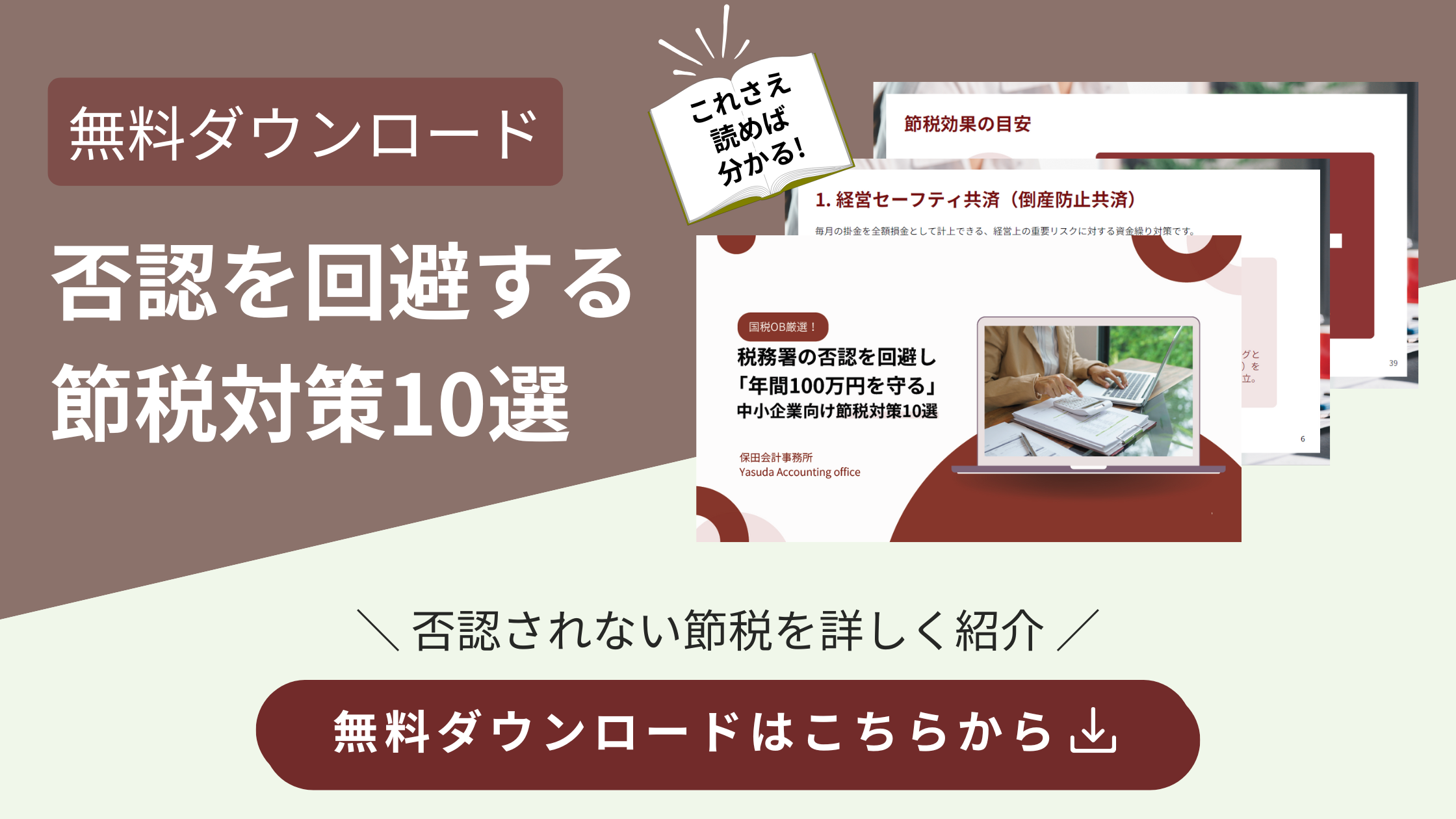税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
近年の副業やフリーランスの拡大に伴って、「夫婦で起業」や「夫婦で会社設立」といった選択肢を検討するご夫婦が増えている印象です。また、そのような方からは「夫婦で会社を設立したら節税になるって聞いたけど本当?」「デメリットや注意点はないの?」といった質問を受けることが多いです。
そこで今回は、夫婦での会社設立を検討している人向けに「夫婦で会社を設立するメリット・デメリット」、「夫婦で会社設立を検討すべき人の特徴」等を詳しく解説します。
Table of Contents
1.夫婦で会社を作る人が増えている背景とは?
はじめに、「夫婦で会社を作る人が増えている背景」や「夫婦起業が注目される理由」などを確認します。
(1)夫婦で会社を作る人が増えている背景
共働きが当たり前となった現代社会では、単に「二人で収入を得る」だけでなく、「夫婦でビジネスを運営する」という選択肢が現実味を帯びています。
背景には以下のような社会的な変化が考えられます。
| ✓テレワークや在宅ワークの普及
✓フリーランス(業務委託)の広がり ✓働き方改革による副業解禁 ✓仕事よりプライベートを重視する人の増加 |
こうした流れの中で、「信頼できるパートナー=配偶者」と共にビジネスを立ち上げるというモデルが注目されています。
(2)夫婦起業はなぜ注目されているのか?
夫婦起業が注目される理由は、節税や社会保等の有利さだけではありません。次のような点でも優れているとされています。
| ✓生活と仕事の一体化を図り、ビジネスと家庭を柔軟に両立できる
✓家族のサポート体制が確立しやすい ✓お互いの得意分野を活かした事業運営が可能 ✓社会的にも「夫婦経営=安定感・信頼感がある」と評価されやすい |
具体的なメリット・デメリットは以下の通りです。
2.夫婦で会社を設立する6つのメリット
夫婦で会社を設立する最大のメリットは、節税と経営の柔軟性の両立ができる点で、それ以外にも、事業運営上の実務面や将来設計において多くの利点があります。そこで、ここでは、6つのメリットを確認します。
(1)所得分散による節税効果
法人を設立すると、夫婦それぞれに役員報酬や給与を支払うことが可能になります。これにより、所得を分散させて所得税の負担を軽減することができます。
個人事業主の場合には、全ての所得は事業主一人に集中し、所得が増えるほど高税率が適用される「累進課税」となりますが、法人化することで、収入を適切に分け合うことができ、次のような節税効果を期待することができます。
<所得分配の違い等>
| 区分 | 個人事業主 | 夫婦で法人設立 |
| 所得税の仕組み | 累進課税(最高45%) | 給与支払いで税率の適正化が可能 |
| 所得の分配 | 不可(原則1人の収入) | 可能(配偶者に役員報酬や給与を支給) |
| 控除対象 | 青色申告控除など限られる | 給与所得控除が活用できる |
(2)社会保険料の最適化
法人を設立した場合、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が発生しますが、これを逆手に取ることで、次のように老後の年金対策や保障の充実というメリットにもつながります。
| ✓将来の年金受給額が増える
✓健康保険の給付(傷病手当金・出産手当金等)も受けやすくなる ✓扶養関係から脱することで、自由な働き方がしやすくなる |
(3)意思決定の速さ
夫婦は日常から意思疎通が取れているため、経営上の判断がスピーディーに進められるだけでなく、外部の役員に比べ経営方針もブレにくいとされています。
(4)信頼関係を活かした役割分担ができる
夫婦ならではの信頼関係をビジネスに活かせば、スムーズな役割分担が可能になります。
例えば、以下のように、スキルや性格に応じて分担することで、経営の効率化が図れます。
| 夫:営業・商品開発・財務管理
妻:経理・総務・顧客対応・SNS運用 |
また、意見が対立した場合でも、根本的な信頼関係があれば冷静な議論ができ、長期的な経営パートナーとして成長していくことができます。
(5)経費の活用がしやすくなる
法人になると、個人事業主では認められにくかった次のような支出も、事業経費として計上しやすくなります。
| ✓家賃や水道光熱費(自宅兼事務所の場合の按分)
✓通信費(電話代やインターネット代) ✓出張費、打合せ費用(夫婦での業務活動含む) |
これにより、可処分所得を大きくなり、手元に残るお金も増やすことができます。
(6)将来的な相続や事業承継がスムーズになる
法人化しておくことで、将来的に事業を子どもに承継する際のハードルが下がります。個人事業の場合は名義が事業主一人に固定されているため、相続時にトラブルになりやすいですが、法人であれば株式の持分によってスムーズな承継が可能です。
また、会社名義で資産を保有している場合、個人資産よりも課税調整がしやすく、相続税対策としても有効です。
3.夫婦で会社を設立する4つのデメリットと注意点
夫婦での会社設立にはメリットだけでなく、デメリットもあります。そのため、ここでは、特に注意すべき4つのデメリットとその対策について確認します。
(1)プライベートとビジネスの境界が曖昧になりやすい
最大の注意点は、「家庭」と「仕事」の線引きが難しくなる点です。
具体的には、「夫婦の会話がすべて仕事の話になってしまう」、「仕事のストレスが家庭にも影響を及ぼす」、「休日や就業時間のメリハリがつけにくい」」といった問題が挙げられます。
<解決策>
| ✓仕事とプライベートの会話時間を意識して分ける
✓毎週ミーティングを設定し、業務上の話はそこで完結させる ✓家でも「仕事の時間」と「オフの時間」を意識的に分ける |
(2)トラブル時に夫婦関係に悪影響を及ぼす可能性
経営がうまくいっている間は問題ありませんが、業績の悪化や経営方針の対立などの問題が生じたときに、夫婦関係にも緊張が走ることが考えられます。
<解決策>
| ✓事前に役割と責任の境界線を明文化しておく(定款や業務分担表)
✓第三者(税理士、顧問など)を間に入れ、冷静なアドバイスをもらう ✓収入が不安定になる時期の生活費のルールをあらかじめ決めておく |
(3)雇用契約・給与支払いに関する法的な注意点
夫婦とはいえ、法人内では「役員・従業員」としての扱いになります。
そのため、相場を超える役員報酬や根拠のないない給与を設定してしまうと、税務署から「過大である」「経費性がない」と指摘され、否認されるリスクがあります。
<解決策>
| ✓配偶者への給与や報酬額は、相場を調査し、妥当な水準で設定
✓税理士と相談し、役員報酬や使用人給与の区分を明確に ✓労働契約書を取り交わす等、勤務実態の客観的な証拠を残すように努める |
(4)社会保険料の負担が増えることがある
法人化することで事業者には社会保険の加入義務が生じますが、これにより、夫婦にとっても、社会保険料の負担が増えたり、扶養の適用外になることで手取りが減ったりすることがあります。
<社会保険に関する比較表>
| 項目 | 個人事業主 | 法人(役員) | 法人(従業員) |
| 健康保険 | 国民健康保険 | 社会保険(健康保険) | |
| 上記の保険料 | 所得割:12%ほど
均等割:7.6万円ほど (限度額106万円ほど) |
一般:9.91%
40歳~64歳:11.5% |
|
| 年金制度 | 国民年金(第1号) | 厚生年金(第2号) | |
| 上記の保険料 | 20万円ほど | 18.3% | |
| 加入義務 | 加入が必要
(任意継続等は除く) |
加入が必要
(非常勤は非加入が認められることもある) |
年収130万円(月収10.8万円)を超えると、扶養から外れ、加入が必要 |
| 保険料負担者 | 全額自己負担 | 会社と個人で折半 | |
| 給付内容 | 限定的 | 手厚い(傷病手当金など) | |
<解決策>
| ✓配偶者を役員とする場合には、非常勤役員とする
(合同会社の業務執行社員は年金事務所の判断で非常勤と認めてもらえないケースがあるため注意が必要) ✓配偶者を非常勤役員や従業員とする場合でも、年収130万円を超えると扶養から外れ、原則として国民健康保険への加入が必要となるため、報酬額の設計に注意 ✓長期的には厚生年金の方が年金受給額が多くなることが予想されるため、中長期視点で判断 ✓社会保険料を「必要経費」として捉え、節税とのバランスを考慮 |
4.夫婦で会社設立を検討すべき人の特徴とは?
ここでは、夫婦での会社設立をおすすめできる人の特徴を解説します。
これらに当てはまる人は、単なる制度メリットだけでなく、ライフスタイルやキャリアビジョンとの整合性という面でも、法人化による恩恵を受けやすい傾向にあります。
(1)副業収入が年間300万円以上ある
副業として始めた事業が軌道に乗り、年間売上が300万円を超えるようになると、給与を含めた所得も700万円近くになってくると思います。このような状況になると個人事業主のままだと税負担が重くなってきます。
例えば、以下のようなケースでは法人化を検討する価値があります。
| ✓夫がIT関連会社から年間600万円の給与をもらっている状況で、副業のWeb制作業で売上が年間300万円超あるケース
✓今後も顧客が増え、さらに売上が伸びる見込みがあるケース |
このような状況では、所得分散による節税や、社会保険の整備を進めることで、金銭面・制度面ともにメリットが見込めます。
(2)配偶者がすでに事業に関わっている
配偶者が業務補助、SNS運用、経理などのサポート等ですでに事業に何らかの形で関与している場合には、法人化することで正当な報酬を支払うことが可能となります。
夫婦それぞれに役員報酬や給与を支払うことにより、所得を分散させて所得税の負担を軽減することもできます。
(3)節税・社会保険コストを本格的に考えている
将来的な事業成長を視野に入れて、税金や保険料の負担を最適化したいと考えている人にとっては、法人化は非常に有効な選択肢です。
<法人化によって得られる主な節税・コスト最適化ポイント>
| ✓所得税の圧縮(配偶者への役員報酬や給与支払いによる所得分散)
✓経費計上の幅の拡大 ✓厚生年金への切り替えによる老後対策 |
これらは、単なる「節税テクニック」ではなく、中長期のライフプランと連動した資金戦略にもなります。
(4)将来的にフルタイムの夫婦経営を視野に入れている
現在は副業による事業運営であっても、「いずれは夫婦で独立したい」「会社を辞めてフルタイムで事業に集中したい」というビジョンがある場合には、早めに法人化をしておくことで以下のような利点があります。
<早期法人化の利点>
| ✓銀行口座や事業の信用が法人名義で整う
✓融資申請などの準備がスムーズになる ✓社会保険や雇用契約の制度設計が事前にできる ✓未来志向の準備がゆっくりとできる ✓夫婦での働き方を長期的に整備できる |
5.その他の参考情報
夫婦での会社設立にあたっては、次の記事もご参考になさってください。
個人事業主との違いや選ぶべき会社形態はこちら:
【夫婦で会社設立①】個人事業主との違いや選ぶべき会社形態等を網羅的に解説!
配偶者(妻)は役員と従業員のどちらがいいかについてはこちら:
【夫婦で会社設立③】配偶者(妻)は役員と従業員のどちらがいいか詳しく解説!
夫婦の役員報酬・給与のシミュレーション結果についてはこちら:
【夫婦で会社設立④】夫婦の役員報酬・給与のシミュレーション結果を解説!
6.まとめ
以上今回は、夫婦での会社設立を検討している人向けに「夫婦で会社を設立するメリット・デメリット」、「夫婦で会社設立を検討すべき人の特徴」等を詳しく解説いたしました。
夫婦での会社設立には、所得分散による節税効果、社会保険制度の活用、役割分担の柔軟性、事業承継のしやすさなど、多くのメリットがあります。特に、すでに副業収入が一定以上あり、配偶者が何らかの形で事業に関与している場合や、将来的に夫婦で本格的にビジネスを育てていきたいと考えている場合には、法人化は非常に有効な選択肢となります。
一方で、「家庭と仕事の境界が曖昧になる」「トラブルが夫婦関係に影響を及ぼす」「社会保険料の負担が増える」といったデメリットもあるため、慎重に検討することも必要です。制度上のメリットだけでなく、夫婦間の価値観やライフスタイル、今後のキャリアビジョンとも照らし合わせて、ベストな形を探ることが大切です。
夫婦での会社設立を検討すべき人とは、副業収入が増えてきた人、節税や社会保険のコスト最適化を本格的に考えている人などです。特に将来的に、フルタイムで事業を運営したいと考えている夫婦にとっては、早期に法人化することで、信頼性の高い事業基盤を早めに築くことができます。
夫婦で会社を設立すべきかどうか判断に迷った場合には、「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループなどの専門家に相談し、自社の状況や働き方に応じたシミュレーションを行うことをおすすめします。
夫婦という最も身近で信頼できるパートナーと、制度を最大限活用しながら、持続可能で豊かなビジネスライフを築いていきましょう。