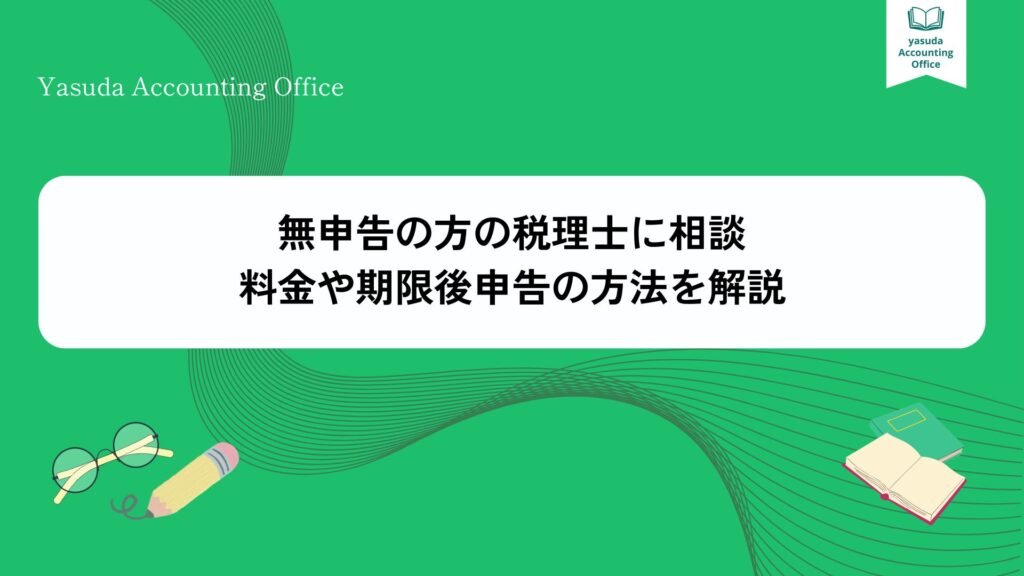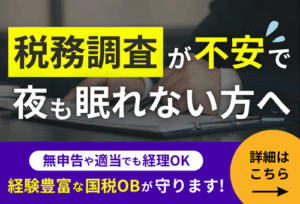税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
「申告が遅れてしまった」「どこから手を付けるべきか分からない」。こうした状況では、延滞税や無申告加算税の負担が日々増加します。
無申告とは、法定期限までに申告書を提出していない状態を指し、放置すると税負担だけでなく与信や取引の信用にも影響します。当事務所は無申告からの期限後申告を短期間で整える体制を備えており、申告書の作成と提出、納付方法の案内まで一貫して支援します。
このページでは、無申告が発覚しやすい理由、費用の目安と増減要因、短期間で申告に到達する実務手順、提出後の税務署対応や分納の検討ポイントを解説します。まずは必要最低限の資料を揃え、最新年度から順に申告を進めることで、金銭的な負担や手間を抑えられます。
※お問い合わせはこちら
【無料相談・最短対応】
初回相談0円/オンライン・全国対応/平日9:00–18:00
【対応範囲】
期限後申告の作成・電子申告、税務署対応(書面・電話)、納付方法の案内、分割納付の相談支援
Table of Contents
無申告とは?無申告の定義・対象・リスクを紹介
ここでは、無申告の意味や対象、よくある勘違い、放置した場合のリスクまでを初心者にもわかりやすく紹介します。
要点
- 定義:法定期限までに申告書を提出していない状態を無申告といいます。
- 対象:個人事業主、フリーランス、法人、相続・贈与で申告義務が生じた個人が対象です。税目ごとに申告要否と期限が異なります。
- 違い:期限後申告は遅れても提出済みの状態、未納は申告済みだが納税未了の状態です。無申告は提出自体がない点で異なります。
無申告の基本的な意味
無申告とは、本来の申告期限までに税務申告書を提出していない状態のことを指します。提出が遅れた後に申告する場合は期限後申告となり、まったく提出していない状態が続くと無申告のまま扱われます。納税額が0の見込みでも、申告義務がある人や会社は申告書の提出が必要です。
だれが対象になるか
対象は個人事業主、フリーランス、法人、相続や贈与で申告義務が生じた個人など広く及びます。所得税、消費税、法人税、地方法人税、相続税や贈与税など、税目ごとに申告の要否や期限が決まっているため、自分がどの税目で義務を負っているかをまず確認することが重要です。
無申告と期限後申告の違い
期限後申告は、期限に遅れたものの申告書を提出している状態です。一方、無申告は提出がない状態が継続していることを指します。どちらも延滞税の対象になり得ますが、期限後申告は早く提出するほど負担が軽くなりやすく、無申告を続けるよりも明らかに不利が少なくなります。
無申告と未納の違い
無申告は申告そのものを出していない状態で、未納は申告はしているが税金を期限までに支払っていない状態です。両者は性質が異なり、求められる対応も違います。無申告はまず申告書の提出が最優先で、未納は納付や分割納付の計画づくりが中心になります。
よくある無申告のケース
開業初年度で帳簿付けが追いつかず申告が間に合わなかったケース、売上は少額だから大丈夫だと思い込んで提出しなかったケース、会社を休眠させたつもりで申告や届出を止めてしまったケースなどが代表例です。少額でも継続的な入金がある、請求書を発行している、給与以外の収入があるといった場合は、原則として申告の検討が必要です。
放置した場合の主なリスク
無申告を続けると、延滞税が日々加算され、状況によっては無申告加算税や重加算税の対象になることがあります。個人や法人の青色申告の承認取り消しが生じる可能性もあり、欠損金の繰越などのメリットを失うことがあります。融資や取引先との信用にも影響が出やすく、後からまとめて整えるほど作業量とコストが増える点も注意が必要です。
無申告はなぜ発覚するのか?
ここでは、無申告発覚までの年数の目安と見つかる仕組みを紹介します。
無申告がバレる目安は3〜7年
無申告が見つかる期間は、一般に3年が中心ですが、取引内容に不自然な点や証憑の欠落が多い場合には5年、意図的な隠ぺいが疑われる場合には7年までさかのぼって確認されることがあります。どの程度の期間を対象にされるかは、業種、取引の複雑さ、金額規模、帳簿や証憑の整備状況などで変わります。
たとえば、売上の入金が継続してあるのに申告が無いケースや、現金取引が多くて裏付けが弱いケースでは、対象年数が広がりやすい傾向があります。
ポイント
- 通常:3年(帳簿・証憑が概ね整っている場合)
- 証憑の欠落や不自然な入金が多い場合:5年
- 仮装・隠ぺいが疑われる場合:最長7年
バレる仕組みは支払調書・口座照会・反面調査・インボイス突合
無申告が露見する経路は複数あります。報酬や配当などに関する支払調書によって収入の手掛かりが税務署に届くほか、銀行口座の入出金の動きから事業収入が推測されることがあります。取引先や外注先を通じた反面調査で売上実態が把握されることもあります。さらに、インボイス制度の導入後は、買い手側の仕入税額控除の要件確認の過程で、売り手側の登録や申告の有無が突き合わせで分かりやすくなりました。
こうした情報が組み合わさることで、無申告は偶然ではなく仕組みとして見つかりやすくなっていると考えてください。
発覚の主な経路
- 支払調書:報酬・料金、配当などの支払情報が税務署に提出され、収入の手掛かりとなります。
- 口座照会:銀行口座の入出金履歴から事業収入が推測されます。現金化サービスや決済サービスの入金も対象になり得ます。
- 反面調査:取引先・外注先への照会で売上や取引実態が確認されます。請求書・領収書の整合性も確認対象です。
- インボイス突合:買い手側の仕入税額控除の確認過程で、売り手の登録状況や申告状況が照合されます。
無申告の税理士費用の相場
ここでは、契約形態ごとの一般的な金額感と、金額が増減しやすい要因を紹介します。
スポット契約の費用目安
スポット契約は、単発で期限後申告や決算申告だけを依頼する形です。個人は1期あたりおおむね20万〜40万円、法人は30万〜50万円が目安です。
普段の経理は自分で管理し、まずは無申告がいくらで片づくのかを判断したい人に向いています。対象年の売上規模、証憑の状態、消費税の有無、固定資産や在庫の取り扱いによって必要作業が変動し、見積りも変わります。
金額が上下しやすい要因
- 仕訳件数と売上規模(件数が多いほど作業量が増える)
- 証憑の整備度(通帳・カードのCSV有無、領収書の欠落)
- 消費税の課税区分・インボイス対応の要否
- 固定資産・在庫の評価や期末調整の有無
- 納期の厳しさ(短納期は人員増で費用が上がる)
顧問契約の費用目安
顧問契約は、毎月の記帳チェックや相談対応に加えて年次決算までを含める形です。個人は月額2万〜4万円に加え、決算時に数か月分の追加が発生するのが一般的で、法人は月額3万〜5万円に加え、決算時に数か月分の追加が発生する水準がよく見られます。
月次の段階から数字を整えられるため、節税提案や資金繰りの助言、税務調査の事前準備、必要に応じた分割納付の相談まで一気通貫でサポートを受けられます。無申告の年を片づけた後に再発防止と運用の平準化を図りたい場合に相性が良い契約です。
含まれる主な範囲
- 月次の記帳チェックと問い合わせ対応
- 四半期レビュー、年度決算、電子申告
- 分割納付の相談支援、税務調査の事前準備
顧問契約を選ぶ判断基準
- 取引量が多く月次で管理しないと遅延が生じやすい
- インボイス・課税区分の継続管理が必要
- 銀行与信や取引先提出書類の定期整備がある
金額はデータ量と納期によって上下する
費用は年商が大きいほど仕訳件数が増え作業量が膨らみ、対象年数が長いほど復元と確認の範囲が広がるため高くなる仕組みです。帳簿や証憑の整備度合いによっても差が出やすく、通帳やカードのCSVが揃っている場合は作業が圧縮され、紙中心で抜け漏れが多い場合は確認と突合の工数が増えます。
さらに、提出期限が迫っているなど納期が厳しいと人員を厚く投入する必要が生じるため、同じ内容でも短納期のほうが費用は上がりやすくなります。
追加費用になりやすいポイント
追加が発生しやすいのは、仕訳の大規模な復元が必要なケース、期末在庫や棚卸資産の評価に手戻りがあるケース、消費税やインボイス対応で課税区分の見直しや登録状況の整理が必要なケース、税務調査への立ち会いや反面調査への対応が想定されるケースです。
紙の証憑が中心でスキャンや入力から始める必要がある場合、現金取引が多くて裏付けを入出金ベースで遡る必要がある場合、過年度に取引先側の資料と突合して矛盾がないかを確認する場合は工数が増えがちです。
なお、売上が0でも法人は均等割などの負担が生じることがあるため、休眠会社であっても費用と作業内容を事前に確認しておくと見積りの誤差を抑えられます。
追加費用になりやすい条件(要点)
- 大規模な仕訳復元や現金出納の突合が必要
- 期末在庫の評価や固定資産の整理に手戻りがある
- 消費税の課税区分の見直しやインボイス登録状況の整理が必要
- 反面調査の可能性や税務調査の立会いが想定される
見積り時にご用意いただきたい項目
- 申告対象年数と各年の売上規模(概算で可)
- 通帳・クレジットカード明細のCSV有無
- 主要な請求書・領収書の保管状況
- 固定資産・在庫・借入の有無
- 消費税の課税状況(免税・簡易・本則)とインボイス登録の有無
- 希望納期(提出希望日)と分割納付の要望
無申告の人がやるべきこと
ここでは、無申告の方が今すぐ着手すべき実務の流れを紹介します。
まずはこれだけ揃える(チェックリスト)
- 通帳の入出金履歴(CSV出力が可能であればCSVを用意)
- クレジットカード・決済サービスの明細(CSV推奨)
- 発行・受領した請求書と領収書(電子データがあれば原本の写しも併用)
- 期末在庫の数量メモと評価の根拠(品目ごとの単価が分かる資料)
- 固定資産の購入日・金額・耐用年数の分かる資料(リースを含む)
- 借入の残高と返済予定表(利息と元金の区分が分かるもの)
- 消費税の課税区分とインボイス登録の有無(登録番号があれば記載)
※上記が揃い次第、申告書の下書きと納付方法の選択(窓口・ペイジー・口座振替・クレジットカード)を並行して検討します。
無申告の人はまず期限後申告へ
税務調査の通知を受ける前に自ら期限後申告へ進むと、科される加算税が軽くなる可能性が高まります。
先に出すことで、無申告の状態を長引かせない意思と是正の姿勢を示せるため、金銭面の負担だけでなく、今後のやり取りのスムーズさにも良い影響があります。
放置して期間が延びるほど、延滞税は日々積み上がり、対象年数も広がりやすくなります。迷っている間に費用が静かに増えていくため、早めの提出が結果的に最も安上がりになります。
必要書類は完璧でなくてよいので提出を先行させる
無申告を短期で解消するポイントは、完璧な資料集めが終わるのを待たず、まず期限後申告に必要な骨格だけを素早く揃えることです。
具体的には、通帳の入出金履歴やクレジットカード明細、発行・受領した請求書と領収書、主要な契約書、期末時点の在庫数量と評価のメモ、固定資産の購入日や金額と減価償却の情報、借入の残高や返済予定の明細といった基礎データを、年ごとに大づかみにまとめます。
完全性よりも、売上と入金、仕入や経費と支払の対応関係が追える最低限の線で先に形を作ることが大切です。
この時点で申告書の下書きを作り、延滞税がいつまで、どれくらい増えるかの概算を算出し、同時に税務署への分割納付の相談可否や支払計画のたたき台を用意すると、その後の段取りが一気に現実的になります。
提出順序は新しい年度から過年度がおすすめ(資金繰りと与信への影響を抑えるため)
提出は、新しい年度から過年度へと後ろにさかのぼる順で進めると、最新の与信や取引への影響を抑えやすく、資金繰りの見通しも立てやすくなります。
提出時には、売上・請求・入金の突合を一覧にした整合表を添え、どのデータを根拠に数字を確定したかを簡潔に示すと、補足の問い合わせが少なくなります。あわせて、翌月以降の月次処理の締め日、証憑の集め方、インボイスの発行体制など、運用をどう改善するかの計画を一枚にまとめて提示すると、是正の意思が明確になり、やり取りが円滑に進みます。
こうした提出順序と説明の工夫は、同じ内容でも受け止め方を変え、結果として加算税の評価やその後の対応のスムーズさに影響します。
税理士に相談するのが1番最短のルート
いちばん早く安全に終わらせる近道は、早い段階で税理士に相談することです。
未申告の年数と売上の目安、手元にあるデータの種類と状態、いつまでに出したいか、支払いに使える資金の範囲を伝えるだけで、作業の順番、必要資料、申告までの工程、延滞税と加算税のおおよその見込み、分割納付を含む支払い計画が具体化します。
実務の段取りとコミュニケーションを専門家がリードすることで、迷いなく進められます。
無申告の人が税理士に依頼するメリット
ここでは、無申告を早く安全に片づけるうえで税理士に頼むメリットを紹介します。
正確な期限後申告で加算税や延滞税のリスクを抑えられる
期限後申告に必要な書類と手順が整理され、数字の整合を確かめながら申告書まで一気に仕上げられます。
どの金額をどの根拠で記載したのかが明確になるため、提出後に訂正を求められたり、説明が噛み合わなくなったりするリスクが下がります。結果として加算税や延滞税の負担が膨らむ事態を防ぎやすくなります。
作業時間が短縮され本業に集中できる
通帳やカード明細の取り込み、仕訳の復元、証憑との突合、申告書の作成といった細かな作業を税理士が引き受けます。
止まりがちな作業に締切と段取りが付き、予定どおりに前へ進むため、経営や営業に時間を回せるようになります。
融資や取引で必要な書類を適切な形でそろえられる
決算書や申告控、総勘定元帳、試算表などを相手先の求める形式で準備できます。提出のタイミングと内容が整うため、審査や取引の場面で説明がしやすくなり、信用の回復や新規の相談にも進みやすくなります。
インボイス対応とあわせて再発防止の体制を整えられる
登録の要否や時期、請求書の様式、課税区分の見直しを同時に進められます。取引先の照合に耐えられる運用に切り替えるとともに、月次の締め日やデータ連携のルールを固めることで、申告遅れの再発を防ぎやすくなります。
安全な税理士を選ぶために聞くべき質問
ここでは、はじめての人でも税理士を迷わず見極められるように、面談で確認すべき質問を紹介します。
無申告対応の実績はどれくらいありますか?
この質問は、経験の量と質を確かめるためのものです。件数は当然として、対象年数や年商の幅、個人と法人の比率、消費税の有無、在庫や固定資産の扱いなど、あなたの状況に近い案件をどれだけ扱っているかが重要です。
直近の似た事例で、初回相談から提出まで何日かかったか、どこで詰まりやすかったか、費用はどのレンジだったかまで聞けると、実際のスピード感と再現性が判断できます。
初動から提出までの具体的な流れを教えてください
ゴールまでの道筋が描けているかを確認します。通帳やカードのCSV収集、仕訳の復元、証憑突合の方法、レビューと修正、申告書作成、提出後のフォローという工程ごとに、あなた側の役割と事務所側の役割、想定日数、ボトルネックになりやすいポイントを説明してもらいましょう。
ここで説明が具体的かつ短く整理されていれば、実務の段取り力が高いと判断できます。
見積の内訳と金額が上下する条件は何ですか?
費用の根拠を明確にする質問です。年商や仕訳量、対象年数、データの整備度、復元の要否、消費税やインボイス対応の有無、税務調査対応や短納期対応など、金額に影響する変数を列挙してもらい、各要素がどの程度の幅で増減に響くかを教えてもらいます。
追加が発生する条件と、その場合の通知タイミングや合意の取り方まで決めておくと、後からのズレを防げます。
分割納付や納税猶予の交渉はどこまで支援しますか?
資金繰りにも直結するため、支援範囲を明確にしておきましょう。税額見込み、収支計画、資金繰り表、分納希望額の根拠など、交渉に必要な資料を誰がいつまでに用意するかを確認します。税務署との連絡を誰が行うか、面談に同席するか、結果が出るまでの目安期間や想定される質問も事前に共有してもらうと安心です。
インボイス対応はどの範囲まで見てもらえますか?
無申告整理と同時並行で、今後の運用を安定させるための確認です。登録の要否判断と登録時期の計画、請求書様式の更新、課税区分や取引区分の見直し、価格設計への影響試算、主要取引先への説明文面の整備、会計ソフト設定の変更など、どこまで実務で並走してくれるかを具体的に聞きましょう。
申告後の月次運用をどう整えますか?
再発防止の設計力を見極めることも大切です。締め日と提出物のスケジュール、銀行やカード、決済サービスの自動連携、証憑の集め方、月次レビューの実施方法、ダッシュボードやチェックリストの提供、担当者間の連絡手順まで聞き、翌月から運用できるレベルの計画に落とし込めるかを確認します。
ここまで具体化できる事務所は、片づけて終わりではなく、その後の安定運用まで責任を持つ姿勢があると判断できます。
よくある質問(FAQ)
無申告はどのくらいの期間さかのぼって確認されますか?
取引の複雑性や隠ぺいの有無で調査対象期間が変動します。一般的には3年、証憑の欠落や不自然な入金が多い場合は5年、仮装・隠ぺいが疑われる場合は最長7年まで遡及されます。対象年数が増えると復元作業と延滞税の負担が増えるため、最新年度から順に早期に提出するのが実務的です。
会社に知られずに申告できますか?
理由として、住民税の徴収方法と書類の送付先を管理することで通知リスクを抑制できます。給与所得者が副業収入を申告する場合は、住民税の徴収方法を「普通徴収」とし、連絡先を本人宛に統一します。提出書類や納付は個人で完結可能です。就業規則の副業規定は別途確認が必要です。
何年分をまとめて出せばよいですか?
理由は与信と資金繰りへの影響を抑えるためです。最新年度→過年度の順で、まず直近年度を期限後申告します。直近年度の確定により、融資や取引で必要な最新の決算書・申告控が整備できます。その後、残りの年分を計画的に提出します。年数が多い場合は分割納付と並行して工程を組みます。
費用が上がりやすい条件は何ですか?
理由は作業量と復元難易度が費用に直結するためです。仕訳件数が多い、通帳・カード明細のCSVがない、領収書の欠落が多い、在庫や固定資産の整理に手戻りがある、消費税の課税区分やインボイス登録の見直しが必要、短納期対応が求められる、といった条件で見積りは上振れしやすいです。
分割納付や納税猶予の相談は可能ですか?
理由として、資金繰りに即した現実的な支払計画が必要だからです。税額見込み、収支計画、資金繰り表、分納希望額の根拠を準備し、税務署に相談します。当事務所は資料作成と手続を支援します。カード納付や口座振替等の納付手段も併記し、手数料や反映時期を踏まえて選択します。
税理士選びにお困りなら「保田会計事務所」にご相談ください
税理士を雇うことには、正確な税務申告や経営の効率化、資金調達や税務調査への安心感など、多くのメリットがあります。一方で費用がかかることや相性の問題といった注意点もありますが、それらを理解した上で適切な選び方をすれば、事業を大きく後押ししてくれる存在となります。もし「無申告をどうすればいいかわからない」「費用と効果のバランスが気になる」「安心して任せられる税理士を探したい」と感じている方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
保田会計事務所では、豊富な経験と最新の知識をもとに、お客様の事業規模や状況に合わせた最適なサポートをご提案しています。税理士選びにお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談方法(いずれかを選択)
- 無料相談フォーム:必要事項を入力して送信してください。
- お電話:平日9:00–18:00(事前予約で夜間・土日可)
ご相談から提出・納付までの流れ
- 相談予約・初回ヒアリング
- 必要資料の提示と収集方法の指示
- 仕訳の復元・整合確認
- 申告書案の作成・ご確認
- 電子申告・控の送付
- 納付方法の案内と資金計画
- 申告後の照会対応・保存体制の整理
税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
・無申告、適当経理や領収書の廃棄もOK
・国税OBによる調査立会で徹底的に交渉
・税務署対応をすべて代行
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし