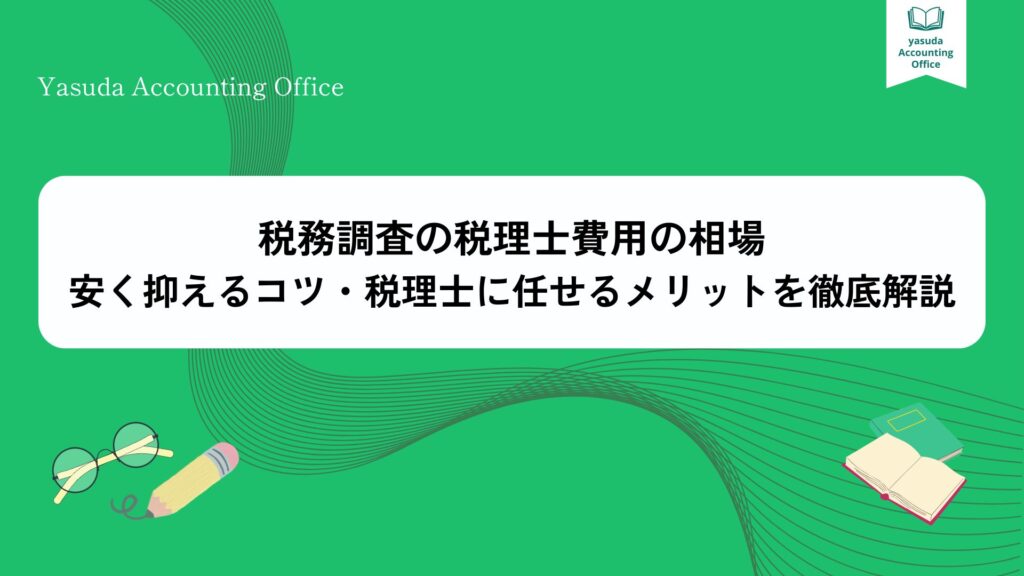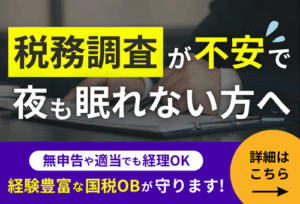税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
「税務調査が入ったけど、税理士に依頼するといくらかかるの?」「税務調査の立ち会いが不安」こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
税務調査は、調査対応の経験や知識が不足していると、思わぬ追徴課税や余計な費用負担につながるリスクがあります。とはいえ、税理士費用がどのくらいかかるのか、どうすれば抑えられるのかは意外と知られていません。
本記事では、以下についてわかりやすく解説します。
- 税務調査時にかかる税理士費用の相場
- 費用が高額になるケースと注意点
- 税務調査の流れと税理士が対応してくれること
- 税務調査の費用を安く抑えるためのコツ
税務調査に不安を抱えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
\税務調査に関するお悩みをお聞かせください/
1、税務調査で税理士にかかる費用相場とは?
税務調査に直面した際、「税理士に依頼するといくらかかるのか?」は多くの経営者にとって気になるポイントでしょう。
ここでは、税理士にかかる基本的な費用相場と、その料金体系について詳しく解説します。
Table of Contents
(1)税務調査の基本費用と料金体系
税理士に依頼する際の費用は、「どんな業務を依頼するか」によって大きく変わります。
①立ち会い費用の相場:1日あたり5万〜15万円が目安
税務調査当日に、税理士が立ち会う場合の費用は、1日あたり5万円〜15万円が相場です。この金額は税理士の経験値や実績、地域差によっても変動します。
- 経験豊富な税務調査専門の税理士 → 10万〜15万円/日
- 一般的な中小事務所の税理士 → 5万〜10万円/日
また、調査が複数日にわたる場合は、その都度日数分の費用が発生する点にも注意が必要です。
②事前準備・修正申告など業務別の料金相場
税務調査は当日の立ち会いだけでなく、以下のような事前・事後の業務にも費用がかかります。
| 業務内容 | 相場 |
| 事前書類チェック・対策 | 5万円〜15万円 |
| シミュレーション対応 | 3万円〜10万円 |
| 修正申告書作成 | 5万円〜20万円 |
| 税務署との交渉 | 5万円〜 |
特に「修正申告書作成」や「税務署との交渉」は、税理士の力量が問われるため、費用は高めになる傾向があります。
③顧問契約かスポット依頼かで異なる料金設定
税務調査時の税理士費用は、顧問契約の有無でも大きく異なります。
| 契約形態 | 特徴 | 費用感 |
| 顧問契約 | 月額契約に含まれる or 割引適用 | 別途対応:5万円〜15万円/日 |
| スポット依頼 | 調査対応のみ単発契約 | 20万円〜40万円/日 |
顧問契約がある場合は、調査対応もパッケージに含まれていることがあり、スポット依頼よりも割安で対応してもらえることが多いです。
(2)高額になりがちなケースとその理由
税務調査にかかる税理士費用は、案件ごとの状況に応じて大きく変動します。特に以下のようなケースでは、相場よりも高額になることが少なくありません。その理由を具体的に見ていきましょう。
①調査対象期間が長い・追徴課税額が大きい場合
税務調査の対象となる期間が3年〜5年など長期間に及ぶ場合、それに比例して調査・確認すべき書類や取引件数も増加します。
- 通常の調査は「3年分」が基本
- 重大な申告漏れが疑われる場合は「5年〜7年分」まで遡及されることも
調査対象期間が長ければ長いほど、税理士が対応する資料整理・取引確認・是正案の作成にかかる工数が膨らみ、結果として費用が高額になります。
また、追徴課税額が大きいケース(数百万円〜数千万円規模)では、税務署との交渉や減額対応も慎重に行う必要があるため、専門性の高い税理士に依頼することで費用が上乗せされることがあります。
②税務署との折衝や書類作成が多い場合
税務調査の過程で、税務署からの指摘事項が多岐にわたる場合、税理士による税務署との折衝業務が増えます。
- 追加説明資料の提出
- 税務調査官との面談・説明
- 修正申告書・反論資料の作成
これらの対応が発生すると、1案件ごとに別途5万円〜10万円程度の追加費用がかかることもあります。
特に「争点が複雑」「法解釈が分かれる」ようなケースでは、専門的な折衝スキルが求められ、税理士の実績やノウハウによって金額差が生まれます。
③特別対応(弁護士連携など)がある場合
調査内容が脱税・重加算税など法的リスクを伴う場合や、税務署との見解の相違が大きいケースでは、税理士単独での対応が難しくなります。
この場合、弁護士との連携対応が必要になり、以下のような追加費用が発生します。
- 弁護士との協議・法的アドバイス → 5万円〜15万円
- 反論書類の作成・代理交渉 → 10万円〜30万円
- 訴訟リスクを見据えた対応 → 別途見積もり(数十万円規模)
これらはスポット対応の範囲を超えるため、案件ごとの特別対応費として別途請求されることが一般的です。
2、税務調査に税理士を依頼するべき理由
税務調査は専門知識と経験が求められる高度な対応が必要な場面です。自分で対応することも可能ですが、リスクと手間を考えると税理士に依頼するメリットは大きいといえます。
(1)追徴課税の減額交渉や不利益を回避できる
税理士の最大の強みは、税務署との交渉力です。税務署からの指摘事項に対して、適切な法的根拠を示しながら反論・交渉することで、追徴課税額を減額できる可能性があります。
- 過去の判例を元にした減額交渉
- 記帳ミスや経理処理の不備を正当化・是正する対応
- 重加算税(悪質な場合に課される税)の回避
税理士が入ることで「納税者側の正当な主張」が通りやすくなり、結果的に数十万〜数百万円単位での追徴課税額軽減につながるケースも少なくありません。
(2)精神的負担を軽減し本業へ集中できる
税務調査は事業主にとって大きなストレス要因です。
- 税務署からの連絡や調査当日の対応
- 記帳漏れや不備を指摘される心理的プレッシャー
- 調査後の是正対応や交渉への不安
これらをすべて自分で背負うのは、精神的にも大きな負担となります。税理士に依頼することで、煩雑なやり取りや交渉は全て専門家に任せられ、本業に集中することができます。
特に中小企業の経営者や個人事業主にとっては、事業活動への影響を最小限に抑えられるという点で、非常に大きなメリットとなります。
(3)修正申告・是正対応の正確性とスピードがある
税務調査後、必要に応じて修正申告や是正対応が求められます。この際、専門知識がないと手続きミスや記載漏れが発生し、追加でペナルティを受けるリスクもあります。
税理士であれば、以下をスムーズに行うことができます。
- 適正な修正申告書の作成
- 必要書類の迅速な準備
- 調査結果を踏まえた最適な是正対応
結果として、調査後のリスクを最小限に抑えつつ、速やかに問題解決を図れるのが税理士依頼の大きなメリットです。
3、税務調査の流れと税理士の具体的なサポート内容
税務調査は突然やってくるものではなく、一定の流れに沿って進行します。税理士はその各ステップで重要な役割を果たします。
ここでは、税務調査の一般的な流れと、税理士がどのようにサポートするのかを具体的に解説します。
(1)税務調査の一般的な流れ
税務調査は、以下のような段階を経て進行します。事前に流れを把握しておくことで、冷静に対応することができます。
- 事前通知
税務署から「税務調査を実施する旨の通知」が届きます。通常は電話連絡の後、文書で正式な通知が送付されます。通知内容には、調査対象期間・調査日程・調査の目的が記載されています。 - 調査当日
税務調査官が会社や事務所を訪問し、帳簿や証憑類の確認を行います。調査対象は売上・経費・資産・負債など多岐にわたります。税理士が立ち会い、調査官とのやり取りをサポートすることで、過剰な指摘や誤解を防ぐことができます。 - 指摘事項の説明
調査後、税務署から調査結果が口頭または文書で説明されます。指摘事項に対して納税者側の意見や反論を述べる場面でも、税理士の適切な対応が重要です。 - 修正申告書の作成・提出
税務署からの指摘に基づき、申告内容の訂正が必要な場合は修正申告を行います。税理士が正確な修正申告書を作成し、提出までサポートします。 - 追徴課税・加算税の納付
修正申告により発生した追徴課税額について、適正な計算を行い、納付手続きを進めます。税理士は延滞税・加算税の軽減措置についても助言を行います。 - 税務署との最終調整・報告
納税者の主張が認められる場合、税務署との交渉によって課税額が軽減されることもあります。税理士が代理人として交渉を行い、最終的な調整・報告まで一貫して対応します。
(2)税理士が行う具体的なサポート業務
税務調査は、事前準備から調査当日、調査後の是正対応まで一連の流れで進行します。税理士は各ステージで的確なサポートを提供し、納税者のリスクと負担を軽減します。ここでは、税理士が実際に行う具体的なサポート業務を詳しく解説します。
①調査前の準備
税務調査の通知を受けた後、最初に重要となるのが事前準備です。税理士は以下のような業務を行います。
- 帳簿・証憑類の確認と整備
売上、仕入、経費、人件費、固定資産など、調査対象となる書類をチェックし、不備やリスクがないかを洗い出します。 - 申告内容の再確認とリスク診断
過去の申告内容と現状の帳簿を突き合わせ、税務署から指摘されそうなポイントを事前に把握します。 - 調査シミュレーションの実施
税務署がどのような質問や指摘をするかを想定し、事業主側の説明内容や対応方針をシミュレーションします。
この段階で問題点を把握し、事前に是正できれば、調査当日のリスクを大幅に低減できます。
②調査当日の立ち会いと税務署との折衝
調査当日は、税理士が納税者に代わり、税務署とのやり取りや交渉を行うことで、調査がスムーズかつ適正に進行するようサポートします。
- 調査官からの質問への対応・説明
税法や会計基準に基づいた専門的な回答を行い、不用意な発言による不利な判断を防ぎます。 - 税務署の指摘に対する反論・交渉
不当・過剰な指摘があった場合、根拠を示しつつ納税者側の立場で交渉を行います。 - 調査の進行管理・スケジュール調整
必要に応じて追加書類の提出や再確認の調整を行い、調査が円滑に進むようサポートします。
税理士が立ち会うことで、調査官との心理的な距離感を適正に保ち、余計な疑念や不安を払拭する効果もあります。
③調査後の是正対応・修正申告書作成
調査終了後、税務署から指摘事項が伝えられます。税理士はこれを受けて、以下のような是正対応を行います。
- 指摘事項の整理と対応方針の立案
税務署の指摘が妥当かどうかを検証し、必要に応じて修正申告・反論書類の作成方針を決定します。 - 修正申告書の作成・提出
指摘内容を反映した適正な修正申告書を作成し、ミスなく提出します。 - 税務署との最終調整・交渉
追徴課税額や加算税の軽減措置について、税務署との折衝を行い、最終的な着地を図ります。
この一連の流れを税理士が主導することで、納税者は大きなストレスから解放された上で不利益を被るリスクを抑えつつ、迅速かつ正確に調査を終えることができます。
4、税務調査の費用を安く抑えるためのコツと注意点
税務調査への対応は、どうしても費用がかかりますが、工夫次第で無駄なコストを抑えることは可能です。ここでは、税務調査にかかる費用を安く抑えるための具体的なコツと注意点を解説します。
(1)事前準備をし調査対象を絞り込む
税務調査で対応する範囲が広がれば広がるほど、税理士の工数が増え、費用も高額になります。そのため、調査対象を絞り込むことが費用削減の第一歩です。
①税理士によるアドバイスの活用
税務調査が入る前に、顧問税理士やスポット契約による「税務リスク診断」を受けておくことで、調査時の対応範囲を限定し、無駄なコストを削減できます。
具体的には、以下の通りです。
- 申告内容や帳簿を第三者目線でチェック
- 税務署から指摘されやすい論点を事前に把握
- 税務調査時に説明が必要な部分を明確化
これにより、調査当日に慌てて対応することがなくなり、税理士の追加工数や余計な書類対応を抑えることができます。
②過去の経理処理・申告漏れチェックをする
税務調査前に、過去の経理処理や申告内容に誤りがないかをチェックしておくことも、結果的に費用削減につながります。
- 領収書・請求書の保存状況を確認
- 売上・経費計上に漏れや不備がないか確認
- 税務署が重点的にチェックする項目(交際費・役員報酬・棚卸資産など)を再確認
こうした事前チェックにより、税務調査時の指摘事項を減らし、対応範囲を狭めることができます。結果として、税理士に支払う立ち会い費用や是正対応費用を最小限に抑えることができるのです。
(2)スポット依頼と顧問契約を使い分ける
税務調査に備える際、税理士との契約形態によって費用感や対応内容が大きく異なります。「スポット依頼」と「顧問契約」の違いを理解し、状況に応じて使い分けることが、無駄なコストを抑えるコツです。
①税務調査対応だけスポット依頼する場合
スポット依頼とは、税務調査対応だけを単発で税理士に依頼する契約形態です。税務調査が初めての方や、これまで自社で申告対応していた中小企業・個人事業主がよく選ぶ形式です。
スポット依頼の特徴
- 必要なときだけ依頼するため初期費用が抑えられる
- 調査対応に特化した専門税理士を選べる
- 顧問契約のような継続費用が発生しない
ただし、調査直前に依頼すると準備期間が短く、割高な緊急対応費用が発生するケースもあります。また、事前に会社の状況を把握していない税理士の場合、スムーズな対応に時間がかかることもあります。
②長期的視点で顧問契約を結ぶ場合
一方、継続的に税理士と顧問契約を結んでいる場合は、税務調査時も迅速かつ的確な対応が受けられるという大きなメリットがあります。
顧問契約の特徴
- 月額顧問料に調査対応が含まれる・または優遇料金で対応してもらえる
- 会社の経営状況・税務リスクを日頃から把握しているため、調査時の対応がスムーズ
- 調査リスクを減らす日常的な経理指導・税務アドバイスが受けられる
- 長期的な節税対策や資金繰りまで総合サポート
特に「毎年の売上規模が大きい」「経理処理が複雑」「将来的に税務調査リスクが高い業種(建設業・飲食業など)」の場合は、スポット依頼よりも顧問契約の方がトータルコストを抑えやすい傾向にあります。
(3)「安さ」だけで税理士を選ばない
税務調査対応の税理士を選ぶ際、「料金の安さ」だけで判断すると後悔することもあります。重要なのは、費用対効果(コストパフォーマンス)の高い税理士を見極めることです。ここでは、その具体的なポイントを解説します。
①成功事例・口コミを確認する
税務調査は、税理士の経験と実績によって結果が大きく左右されます。そのため、選ぶ際には以下の情報をしっかり確認することが重要です。
過去の税務調査対応件数
→ 年間どれくらいの調査案件を対応しているか。実績豊富な事務所は信頼性が高い。
国税OBの税理士が在籍しているかどうか
→国税OBの税理士の方が税務署対応で有利です。国税時代の調査経験を基に調査官の心の中を読んだ税務交渉が可能です。
具体的な成功事例
→追徴課税を減額できた事例や、調査リスクを未然に防いだ実績など、具体例を確認
利用者の口コミ・評判
→料金に対する満足度、対応のスピードや丁寧さ、税務署との交渉力に関する評価をチェック。
こうした情報を集めることで、「安いけれど対応が雑な事務所」と「適正価格で高品質な対応をしてくれる事務所」を見極めることができます。
②見積もり段階での対応力をチェックする
税理士選びで意外と見落とされがちなのが、初回相談や見積もり段階での対応力の確認です。
チェックすべきポイント
- 見積もりの内訳が明確か(曖昧な総額提示は要注意)
- 税務調査に関する具体的な質問に即答できるか
- 想定されるリスクや対策を具体的に示してくれるか
- 納税者の立場に立った提案やアドバイスがあるか
この段階で「親身に対応してくれるか」「専門知識があるか」「信頼できるか」が判断できます。料金だけでなく、この時点での対応品質こそが、調査本番でのパフォーマンスを示すバロメーターといえるでしょう。
まとめ
税務調査で余計な費用やリスクを避けるには、料金の安さだけでなく、経験と対応力のある税理士を選ぶことが重要です。
- 相場は立ち会い5万〜15万円/日、事前準備・修正申告で別途費用
- 事前対策で無駄なコストを抑える
- スポット依頼か顧問契約を状況に応じて選ぶ
- 実績や口コミを確認し、見積もり段階で対応力を見極める
安さに飛びつかず、「信頼できるパートナー」を見つけることが、最終的なコスト削減への近道です。
保田会計事務所では、国税OBかつ会計士ならではの視点で皆様が抱える経営課題を解決します。経理や税務でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
税務調査の連絡が届き不安に思っている方へ
・無申告、適当経理や領収書の廃棄もOK
・国税OBによる調査立会で徹底的に交渉
・税務署対応をすべて代行
経験豊富な国税OBが守ります。
― まずはお気軽にご連絡ください ―
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし