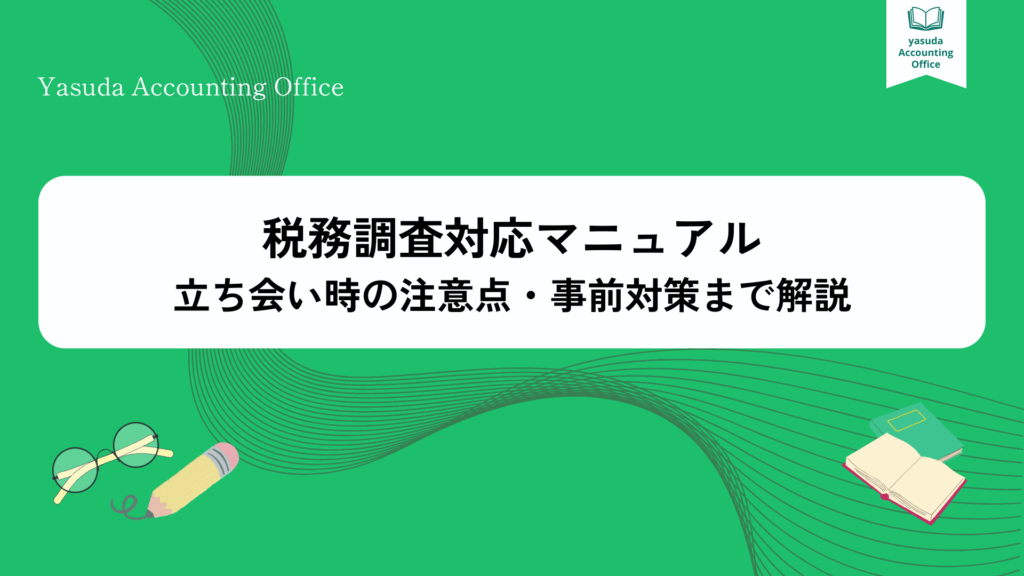税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!
初回 無料相談/平日夜間・土日もOK
―― まずはお気軽にご連絡ください ――
営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし
「税務調査の連絡があった」「うちは大丈夫だろうか」
突然の税務調査の連絡に、不安や緊張を感じる経営者や個人事業主は少なくありません。税務調査は、特別な企業だけに行われるものではなく、どんな事業者にも起こりうるものです。
「税務調査では何が見られ、どこに注意すべきなのか?」を知らずに対応すると、本来払う必要のなかった税金まで請求されてしまうこともあります。
税務調査の対応に不安を感じる方に向けて、以下を詳しく解説します。
- 税務調査の基本知識
- 当日の流れと対応のコツ
- 追徴課税を防ぐ実践的な方法
- 専門家に相談するメリット
税務調査の対応で損しないために必要な基礎知識
税務調査が入ったときに慌てず、損をしないためには、基本的な知識と最新の動向を押さえておくことが不可欠です。まずは税務調査の基礎知識を解説します。
Table of Contents
(1)税務調査には任意と強制の2種類がある
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2つがあり、対応方法やリスクが大きく異なります。誤った対応をしてしまうと、調査が長引くだけでなく、追徴課税や刑事告発のリスクにもつながるため、違いを正しく理解しておきましょう。
①任意調査とは?
任意調査は、一般的な税務調査のほとんどを占めており、事前に調査対象者に「事前通知」が行われます。税務署の調査官が、会社や事業主の元を訪問し、帳簿・領収書・契約書・通帳などを確認します。
主な特徴
- 対象は法人・個人問わず。
- 通知方法は電話または文書(調査日・調査官名の記載あり)。
- 拒否は原則できない(税務署側が「協力義務」を根拠にしている)。
②強制調査とは?
強制調査は、刑事罰を視野に入れた悪質な脱税が疑われるケースで行われます。通称「マルサ」による調査で、令状に基づき、強制的に帳簿やパソコン、現金などを押収します。
主な特徴
- 調査対象は高額脱税・意図的隠蔽が疑われる法人・個人。
- 裁判所の「令状」が必要で、調査前通知なしで突然来る。
- 刑事事件として立件されることもある。
③任意調査でも拒否できない理由
「任意調査だから断っていい」と考えるのは危険です。実際には、税務署は「税務調査の拒否には罰則がある」「協力しない場合は推計課税を行う」と圧力をかけることが多く、事実上拒否は困難です。
また、任意調査の過程で調査官が違法な手法を用いた場合には、弁護士による対応が必要になる場面もあります。拒否よりも、正しく対処する準備が重要です。
(2)税務調査の確率・タイミングは決まっている
「税務調査は突然やってくる」と言われますが、実はある程度の確率とタイミングがあります。自社がどのくらいのリスクを抱えているのかを把握しておくことで、事前対策が可能になります。
①法人・個人事業主の調査確率
国税庁統計によると、税務調査実施率は以下の通りです。
| 対象 | 調査確率(概算) |
| 法人 | 約1.9% |
| 個人事業主 | 約0.7〜1.3% |
②税務署が狙う時期と業種(飲食・不動産・建設・海外取引)
調査は年間を通して行われますが、繁忙期や決算後に集中する傾向があります。
調査が多い時期
- 法人:決算後4〜6ヶ月(特に4月・5月、7月〜11月)
- 個人:確定申告後の7〜9月
狙われやすい業種
- 飲食業(現金商売・帳簿不備が多い)
- 不動産業(高額取引・契約書不備)
- 建設業(下請けとの取引・日雇い人件費)
- 海外取引法人(移転価格・無申告輸出など)
③AIによる異常検知と調査対象選定の仕組みとは
近年、国税庁ではAI(人工知能)を活用して調査対象を選定しています。
AIが検出する異常の一例
- 売上や利益の急変動
- 他社平均と著しく乖離する経費割合
- 類似業種・過去調査データとの不一致
その結果、帳簿が形式的に整っていても、内容が整合していないとAIに検出されやすくなっているため、形式だけでなく実質にも目を向けることが重要です。
税務調査の流れ
この章では、実際の税務調査の一連の流れを紹介します。
(1)税務署から連絡が来る
通常の税務調査(任意調査)は、事前に税務署から電話または文書による通知が届きます。
- 通知内容には、調査日・対象年度・調査官名・調査の目的などが含まれます。
- 通知から調査日までは、2〜3週間程度の猶予があるのが一般的です。
- 調査日時の変更希望がある場合は、早めに申し出ることが可能です。
※ 強制調査(マルサ)はこの限りではなく、予告なしで突然来ます。
(2)調査に向けた準備を行う
通知を受け取ったら、速やかに資料の整理や体制の確認を行いましょう。
- 帳簿・契約書・領収書・請求書などの基本書類を整備。
- 経理担当者、税理士などに連絡・相談。
- 応接室や打ち合わせスペースの準備、書類の動線確認も忘れずに。
※「何がどこにあるか」が即答できる状態が理想です。
(3)調査当日の流れ
当日は、午前10時前後に税務調査官が訪問し、以下のような流れで進みます。
- 調査開始のあいさつと身分証提示
- 会社概要・経理体制・事業内容などのヒアリング
- 帳簿や領収書などの確認
- 質疑応答(特定の取引や仕訳についての詳細確認)
- 初日のまとめ・今後の進行説明(1日で終わらないことも多い)
調査には、代表者または経理責任者が必ず立ち会う必要があります。必要に応じて、税理士が同席することで、より安心して対応できます。
税務調査当日にしっかり対応するために
税務調査当日にしっかりと対応するためにするべき準備と当日の注意点を解説します。
(1)帳簿・領収書・契約書を整理しておく
税務調査の成功可否を分ける最大のポイントは、「帳簿の整備状況」にあります。見た目が揃っていても、実態と一致していなければ容赦なく指摘されます。
①帳簿は時系列で保存し、説明できる状態にしておく
- 現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳などは年度ごとにファイル分け。
- 修正がある場合は、訂正印と修正理由を記載。
- データはPDF印刷・紙保存を推奨(パソコン不具合に備える)。
②領収書・請求書は「紐づけ」が命
- 仕訳との関連がわかるように、インデックスや通し番号を付ける。
- 経費精算書・出張報告書・受領確認書など補足資料も保管。
- レシートは退色対策としてスキャン・画像保存が有効。
③契約書や証憑資料の保管で信頼性が決まる
- 取引先との契約書は署名・押印済み原本で保管。
- 帳簿に記載された内容と契約書の条件が一致しているか確認。
- 電子契約の場合でも、出力して紙で保管すると調査対応がスムーズ。
(2)調査官からの質問・指摘に回答する際は慎重に
調査中に口頭で行われるやりとりも、事実認定に使われる可能性があります。誤解や不利な証言を避けるため、冷静かつ戦略的に対応しましょう。
①「記憶にない」「確認してから回答する」で時間を稼ぐ
質問された内容について、記憶が曖昧だったり即答できない場合には、無理に答えようとせず、「確認のうえ後日回答いたします」と伝えるのが得策です。
その場で不正確な情報を答えてしまうと、後になって整合性が取れなくなり、調査官から「虚偽の申告」とみなされるリスクがあります。あいまいなまま回答するより、慎重に対応した方が結果的に信頼を得られます。
②発言はメモを残す
調査中の会話の内容は、可能な限り記録に残しておくべきです。調査官が複数で来ている場合などは、こちら側の記憶違いを避けるためにも、会話の重要なポイントを逐一メモしておくことが大切です。
③「その場で認める」「口頭で謝罪」は避ける
調査官から何らかの指摘を受けた際、たとえ心当たりがあっても、その場で「それはミスでした」「すみません」と口に出してしまうのは危険です。そうした発言は、後の調査記録に「非を認めた証言」として記録され、反論の余地が狭まってしまいます。
税務調査でよくある追徴課税の原因と今からやっておくべきこと
税務調査において最も大きなリスクとなるのが、「追徴課税」です。調査の結果、申告漏れや不適切な経理処理が見つかると、追徴税額に加えて加算税・延滞税が課され、最終的な納税額は当初の何倍にも膨らむケースもあります。
(1)よくある追徴リスクとその防止策
税務署は、過去の膨大な調査データやAIによる分析をもとに、追徴の可能性が高いポイントを重点的にチェックしています。以下のような典型的なリスクは、調査で非常に指摘されやすいものです。
①現金管理のずさんさ・二重帳簿・架空経費の例
現金商売を行っている事業者では、特に現金の出入りが曖昧なケースが目立ちます。現金出納帳の記帳が漏れていたり、実際の残高と帳簿が合っていない場合、「申告内容に信頼性がない」と判断されかねません。
また、内部用と外部用の帳簿を使い分ける「二重帳簿」や、存在しない取引先に支払ったように見せかける「架空経費」も、典型的な調査対象です。これらは、悪質性が高いと判断されると重加算税の対象となる可能性もあるため、非常にリスクが高いポイントです。
②売上の漏れや期ズレによる指摘リスク
売上計上のタイミングが実態とずれていたり、一部の売上を除外している場合も追徴の原因となります。特に、決算前後の売上処理については税務署も厳しくチェックしており、納品日や役務の提供日と売上計上日の整合性が取れていないと、「意図的な操作」と判断されることもあります。
入金ベースで売上を計上してしまっている場合など、会計処理ルールの誤解も追徴の温床となります。
③家事関連費用の按分ミスや役員報酬の不適切設定
個人事業主や中小法人においては、プライベートと事業の費用を正確に分けることが難しくなりがちです。たとえば、自宅兼事務所での家賃・電気代・通信費などを事業経費として処理する場合、按分比率が実態と乖離していると、指摘を受けやすくなります。
また、役員報酬についても、年度途中で変更したり、実態以上に高額に設定していると「損金不算入」となる場合があり、追徴対象となるため注意が必要です。
(2)追徴を防ぐために今からできること
追徴課税を未然に防ぐには、税務調査が来てから慌てて対応するのではなく、日常的に正確な記帳・管理体制を整えておくことが何より重要です。ここでは、今すぐ実践できる予防策を紹介します。
①平常時からの帳簿体制と月次処理の整備<
帳簿や書類を調査前に急ごしらえで整えようとすると、どうしてもミスや不備が生まれがちです。そのため、普段から月次で帳簿を締め、領収書・請求書と仕訳の突合を行っておくことが非常に重要です。
会計ソフトやクラウド経費精算ツールを導入すれば、作業効率を上げつつ、記帳ミスを減らすことができます。帳簿が「誰が見ても整っている」状態になっていれば、税務調査官の印象も良くなり、指摘を回避しやすくなります。
②節税スキームの見直しと専門家との定期面談
かつて合法とされていた節税スキームが、税務署の方針転換や判例の影響で、否認されるケースが増えています。とくに、形式的な取引で税負担を回避しようとするスキームは、AIによって異常検出されやすくなっているのが実情です。
そのため、定期的に税理士と面談し、スキームが現在の基準に適合しているかをチェックすることが必要です。節税は「攻め」だけでなく「守り」の視点から見直す時代になっています。
③海外取引・仮想通貨・相続など特殊領域の事前対策
国際取引や相続、仮想通貨などの分野では、取引の複雑さから申告ミスが生じやすく、税務署も重点的にチェックしています。たとえば、海外子会社との取引価格(移転価格)が適正であるか、仮想通貨の取得・売却記録が整っているか、相続財産の評価が正確であるかなど、判断に高度な知識を要するポイントが多数あります。
これらの分野は、一般的な税理士ではカバーしきれないこともあるため、専門分野に強い税理士・会計士との連携が非常に重要です。
税理士に相談するメリットは?税務調査の対応が不安な人はプロに相談しよう
税務調査は、経営者や個人事業主にとって精神的にも実務的にも大きなプレッシャーとなるイベントです。「どこを見られるのか?」「どう対応すればいいのか?」と不安を感じたとき、頼りになるのが税務のプロである税理士の存在です。
この章では、税理士に相談・依頼することの具体的なメリットを紹介します。
(1)税務署とのやり取りを代行してくれる安心感
税務調査において、税務署と直接対応するのは緊張するものです。税理士に依頼すれば、調査官とのやりとりを代理人として代行してもらえるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
言い回しや表現を間違えて余計な誤解を生むリスクも減らせます。
(2)帳簿の整備・不備の洗い出しを事前に行える
調査前に税理士と帳簿を見直すことで、指摘されやすいポイントや処理ミスを発見し、修正や補足資料の準備が可能になります。過去の調査で何が問題になったかという“調査官の視点”を知っているからこそ、事前の備えが現実的・実用的になります。
(2)税務調査への立ち会いで現場対応もスムーズに
税理士が調査当日に立ち会ってくれることで、調査官からの質問にも事実関係を整理して的確に回答することができます。担当者が緊張して説明できない場合でも、プロが補足してくれる安心感があります。税務署との“対話の交通整理役”ともいえる存在です。
税務調査に対応できる税理士なら保田会計事務所
税務調査は、すべての事業者にとって無関係ではなく、突然やってくるものです。しかし、正しい知識と準備、そして専門家の力を借りることで、必要以上に恐れる必要はありません。
もし少しでも「不安がある」「うちは大丈夫だろうか」と感じているなら、今すぐ専門家に相談するのが最善の一手です。
保田会計事務所では、国税OB税理士を中心としたチームが、調査対応から事後支援までを一貫して行っています。お困りの際はぜひお問い合わせください。